ピアノを習い始めたばかりのころに、先生に言われることの一つが、
ピアノを弾くときの手の形
ではないでしょうか。
毎回のレッスンで細かく注意され、でもなかなかできなくて、だんだんとレッスンが辛くなり・・・
これ、実際にレッスンを受けている子にあったことで・・
「これ、ホントにやらなくちゃいけないの?」と思うことも、あるのではないでしょうか。
なぜ先生は、口うるさく「手の形」のことを言うのか。
そして、手の形は直さなくてはいけないのか。
ちょっと考えてみました。
私も言います!ピアノを弾く「手の形」
私も、片田舎の生徒数も少ない、小さな小さなピアノ教室の先生ですが、やっぱり言います「手の形」のこと。
それはなぜか。
それはやっぱり、ピアノを弾くにも基本のフォームがある、と考えているからです。
スポーツだと”フォーム”ということがとても重要視され、フォームを整えることは上達に欠かせないことですよね。
例えばバッティング。
ただやみくもにバットを振り回すだけでは、なかなかボールを打つことができない。
でも、フォームを整えることで打てるようになった!とか。
そうなのではないですか?

私、正直言ってスポーツはまるでしませんので、ちょっと自信が無いのですが・・
ピアノはスポーツではないですが、やっぱり基本のフォームがあるのです。
それを整えることで、上達は違ってくると考えています。
スポンサーリンク
手の形を整えるのは「楽に弾くため」
上に挙げた例「バッティング」の場合、フォームを整えるのは、まずは「ボールを打てるようになる」ため。
ボールを打てるようになったら、さらにいろいろと見なおしていくのだと思います。
遠くに飛ばすために、とか、思うところに打てるために、とか。
では、ピアノは何のためにフォーム、つまりは「手の形」を整えるのでしょう。
それは「楽に弾くため」。
と私は思っています。
ピアノって指先を本当に細かく動かします。これは見れば明らかだと思います。
何も考えずただ弾いていると、結構疲れるはず。
というか、まず細かく動かすこと自体が難しかったりします。
「指がうまく動かないのは脳の老化のせい」なんて思うかもしれませんが、そうではありません。
確かに、脳からの指令で指は動いているわけで、脳が大きく関連しているのは事実ですが、そればっかりでは絶対にない!
手の形が整っていないと、必要ないところに力が入って固まり、そのせいで動かしづらくなる、ということは大いに考えられます。
楽に指を動かす。
そのために、手の形を整えることが大事になるんです。
そして、楽に動かせるようになれば、「音色」を追求していくことも、もっと自由にできるようになります。
あんなやわらかい音を出すには・・あんな力強く深い音を出すには・・
憧れの「音」に近づけるようになります。
「手の形」だけではなく
ここまで「手の形」とだけ言ってきましたが、本当は手だけの問題ではありませんよね。
直接的に音を出すのは「手」(指でもありますが)ですし、一番動かす部分でもあります。
なので、「手の形」が焦点になりがちですが、本来は身体全体を考えなければいけません。
椅子の高さ、座り方、頭の位置、肩、腕の位置、力の入れ具合・・などなどを総合的に見る必要があります。
身体全体との関係から手を見ていくということですね。

これってとっても難しいことで、私もまだまだ勉強中です。
つまりはやっぱり「フォーム」なんです。
フォーム;①動きの型。姿勢。
三省堂「大辞林」より
ピアノを弾く「手の形」 直さないとどうなる?
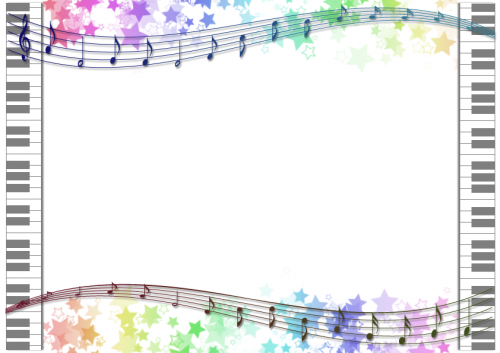
先生からしつっこく言われる「手の形」。これをそのままにしておくとどうなるのでしょう。
私は、2つの弊害があると思います。
- 手や腕などがつかれる・痛くなる
- 弾けない曲が出てくる
手や腕などがつかれる・痛くなる
1つは、手や腕などに疲れを感じたり痛みを感じたりすることです。
それは、そのまま放っておくと腱鞘炎などの故障につながり、下手をすると弾けなくなります。
腱鞘炎の主な原因は、「手首・指の使い過ぎ」
腱鞘とは、骨と筋肉をつないでいる腱を包み、腱が滑らかに動くように支える滑車のような働きをする組織です。腱鞘炎とは、この腱鞘と腱がこすれ合って炎症を起こす病気です。腱鞘炎を起こしやすい人は?
クスリと健康の情報局「腱鞘炎の原因」
腱鞘炎は指の使い過ぎで起こることから、パソコンのキーボードやマウスなどで反射的な操作をしたり、スマホを長時間操作する人、ピアノなど指を多く使う楽器を演奏する人、グリップやボールなどを握るようなスポーツをする人などに多く見られます。
上の引用にもありますが、腱鞘炎がピアノを弾く人に多いというのは、よく知られていることだと思います。
でも、ならない人もいるのは確かで、それはなぜかを考える必要がありますね。
手や腕が丈夫だから?
そんな単純なことではないでしょう!
その1つは、手や腕を酷使しない「楽な弾き方」をしている人なのだと思います。
弾けない曲が出てくる
もう1つは「弾けない曲が出てくる」ということです。
ピアノを始めたばかりの頃はいいんです。
メロディーやリズムはシンプルで、指くぐりなど複雑な動きもありません。
でも、だんだんと難しい曲を弾くようになってくると、手指が動かしにくくなってきます。
楽譜に書いてあることに応えられなくなるんです。
無理をして弾こうとすると痛めることにつながり、結局は「弊害」の1つ目に挙げたことに結び付きます。
「手の形」を整えずにピアノを続けるということは、はじめから弾ける曲の上限を決めてしまっているということです。
いろんな曲を弾きたいと思うのなら
「ピアノを弾きたい」と思う動機は人それぞれだと思います。
ある曲にすご~く感動して、自分でも弾いてみたい、と思う。
ピアノ自体に興味があって、弾けるようになったらステキだな、と思う。
本当に様々な思いがあって、ピアノを始めるのだと思います。
そんな中、ピアノを弾こうと思う人の気持ちは大きく分けると次の2つかな、と思います。
- 大好きな曲1曲を弾けるようになれば満足
- いろんな曲を弾いてみたい
もし、自分の気持ちが2つ目に近いのなら、やっぱり頑張って手の形を整えていった方がいいと思います。
上にも書いたように、手の形に無頓着でピアノを続けることは、自分で弾ける曲の上限を決めてしまうこと。
簡単ではないし、地道な訓練が必要だし、おもしろくも何ともないことかもしれません。
でも、これが「基礎練」だと思って(事実そうですし)頑張って続けてほしいと思います。
実は、自分の教室のレッスンで
「手の形のことをやるのが辛い・・」
こんな告白を受けまして・・
私なりになぜ必要かを考えて、このようにまとめてみました。
考え方の一助になれば、と思います。
(公開日:2018年1月30日 2024年8月7日)

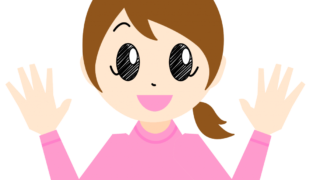

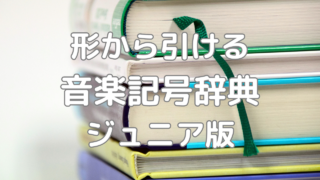
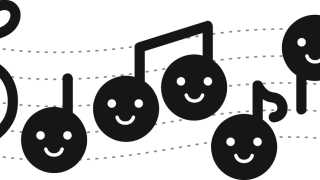




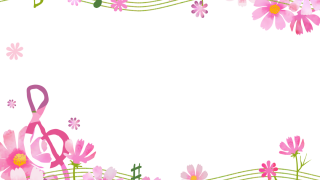




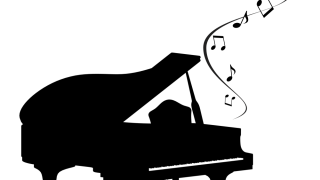




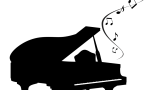
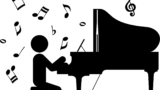
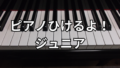

コメント