拍子記号は分数の形で表記されていますが、読むとき、分子の数字が実際の拍子になりますね。
4分の3拍子(3/4)なら3拍子。
4分の2拍子(2/4)なら2拍子。
2分の2拍子(2/2)も2拍子。
では、8分の6拍子(6/8)は・・・?6拍子ではありません!
6拍子であって6拍子ではない。
これはどういうこと?
どう拍子を数えればいいの?
そのあたりを書いていこうと思います。
「拍子」とは?
まず、「拍子」とは何なのか。
そこから話を始めます。
「拍子」とは、音楽辞典には以下のように書かれています。
拍と呼ばれる固定した単位時間の一定数から成る基本的な音楽的時間。
新音楽辞典 楽語(音楽之友社)
「固定した単位時間」とは、拍子記号の分母の数字のこと。
拍子を取る時の単位となる音符です。
そして、「一定数」とは、その音符いくつを一定とするのか、ということですね。
つまり、拍子記号の分子部分のこと。
3つにするのか、4つにするのか、はたまた5つにするのか・・
それを一つのまとまりとするのが「基本的な音楽時間」ということになります。
それが連なっていくことでできる時間の流れが「音楽」ということになりますね。
例:4分の3拍子(3/4拍子)
例えば4分の3拍子(3/4拍子)の場合、
「固定した単位時間」が4。つまり4分音符。
そして、「一定数」が3。
4分音符3つ分が、「音楽的時間」の基本のまとまりということになります。
この「基本的な音楽的時間」ごとに小節線で区切られ、楽譜となっているということですね。
なので、
1,2,3/1,2,3・・・
と数え、3拍子ということになります。
スポンサーリンク
単純拍子と複合拍子
ここで、拍子の種類についても説明をします。
拍子は様々ありますが、「単純拍子」と「複合拍子」に分けられます。
*もう1つ、変拍子(混合拍子)もありますが、ここでは取り上げません。
「単純拍子」と「複合拍子」は、それぞれ以下のような拍子となります。
問題の8分の6拍子(6/8拍子)は「複合拍子」ということですね。
以下で、2つの拍子について詳しく説明します。
「単純拍子」とは
「単純拍子」は、付点音符以外の音符(単純音符)で成り立っている拍子です。
「付点音符以外の音符」ということは、2分音符、4分音符、8分音符を1単位とした、ということですね。
例えば、4分の2拍子(2/4拍子)は、4分音符を1単位(1拍)として数え、2つあるので2拍子となります。
それこそ”単純”に、拍子記号の分子部分がそのまま拍子になるわけですね。
8分の6拍子(6/8拍子)は「複合拍子」
そして「複合拍子」は、「単純拍子」が合わさったものです。
6拍子、9拍子、12拍子があります。
ということで、6/8拍子は「複合拍子」ということです。
6拍子は、「単純拍子」である3拍子が2つ合わさったもの。
つまり、2拍子です。2拍子の1拍分をそれぞれ3分割していると捉えます。
9拍子は3拍子が3つの3拍子。3拍子の1拍分が3分割されている。
12拍子は3拍子が4つの4拍子。4拍子の1拍分がそれぞれ3分割、ということですね。
これは、どういうことかというと・・
「単純拍子は付点音符以外の音符で成り立っている」と書きましたが、「複合拍子」は、付点音符を単位としている、ということになります。
例:8分の6拍子(6/8拍子)
8分の6拍子(6/8拍子)について詳しく見てみます。
8分の6拍子(6/8拍子)は、単純拍子である8分3拍子(3/8拍子)が2つ合わさった拍子。
つまり、「8分音符3つ」+「8分音符3つ」ということになります。
「8分音符3つ」、それは「=付点4分音符」です。

つまり、8分の6拍子(6/8拍子)は、「付点4分音符を1拍とした2拍子」ということになるわけです。
例:4分の6拍子(6/4拍子)
もう一つ例を挙げます。
あまり出てこない拍子ではありますが、4分の6拍子(6/4拍子)です。
4分の6拍子(6/4拍子)は、単純拍子である4分の3拍子(3/4拍子)が2つ合わさった拍子です。
つまり、「4分音符3つ」+「4分音符3つ」ということですね。
「4分音符3つ」とは、「付点2分音符」の長さと同じです。

ということで、4分の6拍子(6/4拍子)は、「付点2分音符を1拍とする2拍子」ということになります。
4分音符が6つだから、「4分音符2つずつに分けて2分音符3つの3拍子」とはなりません。
これが、「複合拍子」の捉え方です。
拍子の数え方の違い
ここまで、「単純拍子」と「複合拍子」の違いを見てきました。
「単純拍子」と「複合拍子」では、拍子を数える時の元となるものが違う、ということが分かったでしょうか。
単純拍子の拍子の数え方
例えば、「単純拍子」である4分の3拍子(3/4拍子)なら、
分母部分が4なので4分音符を一拍として拍子を数え、分子部分が3なので3拍子ということになります。
1,2,3/1,2,3/1,2,3・・・
強、弱、弱/強、弱、弱/強、弱、弱・・・
と数えていきます。
”単純”に書かれている通りに捉えればよいということですね。
複合拍子の拍子の数え方~8分の6拍子(6/8拍子)を例に~
一方「複合拍子」。
例えば8分の6拍子(6/8拍子)では、8分音符3つを一単位として2つ分、と捉えます。
8分音符3つ分は付点4分音符1つと同じ長さになるので、付点4分音符を1拍として2拍子でとらえるわけですね。
1,2,3 2,2,3/1,2,3 2,2,3/・・・
強、○、○、弱、○、○/強、○、○、弱、○、○/・・・
と拍子を数えます。6拍子ではなく、2拍子なのです。
8分の6拍子(6/8拍子)は4分の3拍子(3/4拍子)2つではない!
ここで間違えてはいけないのは、こちら↓
8分の6拍子(6/8拍子)は4分3拍子(3/4拍子)2つではない!
ということです。
先にも書いたように、8分の6拍子(6/8拍子)は
1,2,3,2,2,3/・・・
と拍子を数えます。
なので、3拍子が続いているようにも感じます。
でも、この2つは拍子の数え方が違うのです。
8分の6拍子(6/8拍子)の拍子の数え方は↓
1,2,3 2,2,3/1,2,3 2,2,3/・・・
強、○、○、弱、○、○/強、○、○、弱、○、○/・・・
先にも書いたとおりです。
では、4分の3拍子(3/4拍子)は↓
1,2,3/1,2,3/1,2,3・・・
強、弱、弱/強、弱、弱/強、弱、弱・・・
これも、先に書いた通り。
3つの音符を1拍と捉える8分の6拍子(6/8拍子)。これは、付点4分音符を1拍とする拍子です。
一方、4分の3拍子(3/4拍子)は3つの音符をそれぞれ1拍と捉える拍子。
この違いは、演奏上とても大きなものです。
演奏するときには、きちんと違いを意識しておかなければいけません。
8分の3拍子(3/8拍子)は単純拍子だけど・・
8分の3拍子(3/8拍子)は8分の6拍子(6/8拍子)の半分の拍子ですね。
8分の6拍子(6/8拍子)ほどではないですが、ままよく出てくる拍子です。
8分の3拍子(3/8拍子)は8分音符を単位とする「単純拍子」に入ります。
でも、拍子の数え方は、複合拍子のように8分音符3つを1拍と捉えます。
8分音符3つ=付点4分音符1つを単位とした1拍子、ということになります。
「拍子」あっての音楽
音楽は、一定の拍子の上に成り立っています。
なので、音楽を演奏するには、「拍子」についてきちんと理解しておくことがとても大切です。
初心者の方が、拍子についてぶつかりやすいカベが、8分の6拍子(6/8拍子)ではないでしょうか。
これは8分音符3つで1拍になって・・それが2つだから2拍子で・・
と理屈で理解することも大事。
それと共に、8分の6拍子(6/8拍子)のノリを体感することもとっても大切です。
強、○、○、弱、○、○/強、○、○、弱、○、○/・・・
このノリを感じながら、8分の6拍子(6/8拍子)の曲をいろいろと聞いてみてください。
(公開日:2023年4月18日 最終更新日:2024年2月27日)



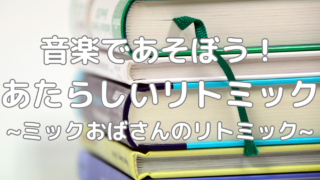
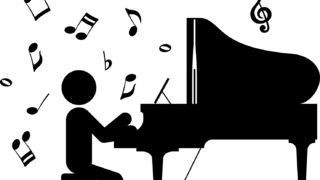
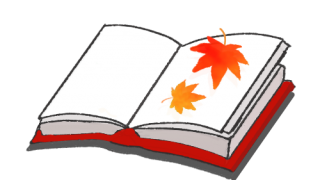


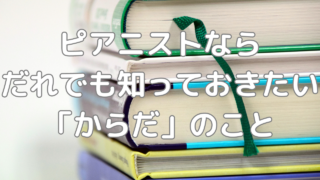
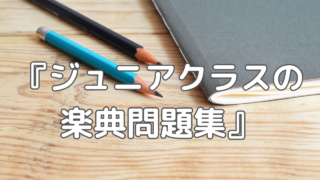



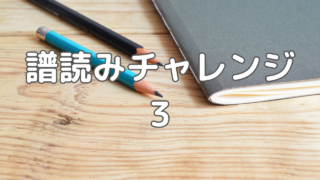
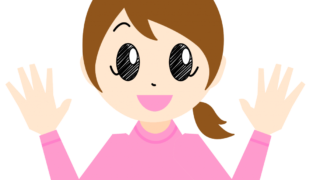






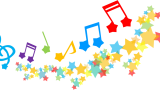
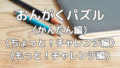
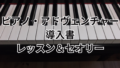
コメント