ピアノ界では超有名な教材『ハノン』。私もひたすらこれを弾いて練習してきました。
「機械的で面白くない」という評価の反面「絶対必要!!」と考える人も多いですよね。
私もやった方が良いと考え、自分の教室のレッスンでは『ハノン』を取り入れています。
『ハノン』のレベルと練習法ついて、私の考えと実際のレッスンで行っていることを交えてまとめてみました。
『ハノン』いつから始める?レベルはどのくらい?

『ハノン』は良い!と聞くけれど、実際いつから始めればよいのか・・
大きな疑問ではないでしょうか?
『ハノン』は教材としてのレベルを考えると、
「ピアノは全くはじめて」という状態で取り入れるのは早すぎる
というのが私の考えです。
ひたすら16分音符を弾く、という形ですし、速度指定も♩=60~と初心者ではかなり速くなっています。
ある程度は指が動かせるようになってからが良いと思います。
ひたすら同じことの繰り返しなので、よく指が動かないうちは無理があります。
また、よほど丁寧に取り組まないと、良くない手や指の使い方で固まってしまう可能性も。
なので、
ある程度弾けるようになって、何か曲を弾いていて、「もっと速くスムーズに動かしたいんだけど‥」と思うようになったころ
でよいのではないでしょうか。
自分の教室でも、まずは『バーナム・ピアノテクニック』などを使って、様々な音型の弾き方を経験することから始めます。
その中で、どうも”つぶ”がそろっていない、指1本1本のコントロールができていない、テンポが保てない、などを感じたら使います。
レベルとしては、だいたい、ブルグミュラーに入る少し手前くらいから。
しかも始めは、『ハノン』を簡単にした教材を使います。
『ハノン』を弾きやすく簡単にしたテキストもたくさん出ています。
まずはそういうものを使ったり、そうした楽譜の一部を抜粋して弾いてもらったりすることから始めます。
関連記事→こちらの記事で『ハノン』を弾きやすくした楽譜2冊を紹介しています。
『全訳ハノンピアノ教本』等を使って本格的に始めるのは、ソナチネに入るころになります。
『ハノン』の練習法 第1部をていねいに

上にも書きましたが、『ハノン』はかなりレベルの高い練習教材です。
ピアノを始めて間もないうちは、第1部をていねいに繰り返し弾くことが良いと考えています。
メトロノームは必須 でも速さにはこだわらず
一般的な『全訳ハノンピアノ教本』を使う場合は、第1部をていねいにゆっくりと進めていくのが良いですね。
その際、メトロノームはきちんと使いましょう。一定のテンポの中に音を入れていくことが大切なので。
でも、速さにはこだわる必要はありません。
第1部の第1番の上部に、
「これからの20曲は、初めメトロノームを60にして練習をし、だんだん速くして108でできるまで弾きます」
と書かれています。
ですが、60でなくてもよいです。
「自分が余裕を持って弾ける最もはやい速さ」が良いですね。
極端にゆっくりにする必要はありません。ゆっくりをたくさん弾けば早く弾けるようになるというものではありませんし。
何度も続けるうち、「自分が余裕を持って弾ける最もはやい速さ」がだんだん速くなっていくはずです。
後述しますが、余裕を持って弾けることがとても大切だと考えています。
関連記事→こちらの記事でメトロノームを使う時の注意点をまとめています。
リズム練習は必須
『ハノン』をやる場合、リズム練習はとても大事です。
一定のテンポの中に正確にリズムを入れていくことで、テンポ感はもとより、つぶをそろえて弾くことにも大いに効果があります。
『全訳ハノンピアノ教本』には、「1番の変奏の例」として、22のリズムの例が載せられています。
その中から比較的弾きやすいものを2つ3つ選んで、メトロノームに合わせて弾きます。
具体的には、3番~11番の8分音符と16分音符の組み合わせ例と、13番と14番の付点のリズムあたりがいいのではと思います。
スムーズに動くようになってきたら、1番2番のアクセントをつけるものや終わりの方のスラー、スタカート、アクセント、付点が様々組み合わされているものに入っていくと良いですね。
速さは、やはり「余裕を持って弾ける最もはやい速さ」で弾くのが良いと思います。
ちょっと弾いてみました。参考になればと思います。
↓ハノン1番 指定の速さ♩=108で弾いています。
↓ハノン1番を「1番の変奏の例」13番と14番で弾いています。
関連記事→こちらの記事で『ハノン』の練習ポイントについてまとめています。
『ハノン』メリットは「余裕」が生まれること
『ハノン』をやる大きなメリット。
それは、「弾いているうちに余裕が出てくる」ということです。
これは、同じことを繰り返していく練習法だからこそのメリットだと考えています。
余裕が出てきて、その余裕で意識を向けてほしいことがあります。
それは、
自分の指がどう動いているのか、どう動かすべきか
ということです。
弾きながら、自分の指の動きによ~く注意を向けて、よ~く感じながら弾くこと。
- どのくらいの力でどこまで動かすのか
- 指の動きはスムーズか
- どんな音を出しているのか
といったことを意識して弾くことで、
- 鍵盤の位置の感覚
- 弾くときの力の入れ具合、抜き具合
などが見えてくるはずです。
それが結果的に「音のつぶがそろう」ということにつながっていきます。
ただただ指を動かすだけではなく、意識的に弾くことがとても大切です。
それをしやすいのが『ハノン』だと考えています。
『ハノン』って必要?
ピアノの練習といえば『ハノン』といってもいいくらい、ハノンは有名な教材です。
一方で、賛否両論ある教材でもありますね。(とはいっても「賛」の方が多いのかな?)
私は、できれば練習に取り入れた方が良いと考えています。
ひたすら曲の部分練習もいいけれど・・
曲をうまく弾けるようになりたいからやる『ハノン』。
でも、曲の弾けない部分は、そこを何度も練習すればいずれは弾けるようになるでしょう。
じゃあ、『ハノン』はいらないんじゃないか・・と思ってしまいますが・・。
私は、「曲の部分練習期間を短くするために」やるといいのではと思っています。
つまり、基礎体力をつけておく、といった意味合いですよね。
苦手な部分でもはじめからある程度弾ける。
そんな力をつけるために、『ハノン』は良いと考えています。
『ハノン』の導入は慌てずに
でも、ピアノを始めた初期から取り入れる必要はないと思っています。
ある程度指が自由に動かせるようになり、必要を感じたら、でよいと考えています。
私の教室では、『全訳ハノンピアノ教材』などを使って本格的に導入するのは、ソナチネくらいからです。
『ハノン』はあくまでも指の訓練の教材です。
これだけに頼るのは間違いだと思いますし、明確な目的をもって使っていかなければいけないと思っています。
(公開日:2017年9月26日 最終更新日:2026年2月6日)


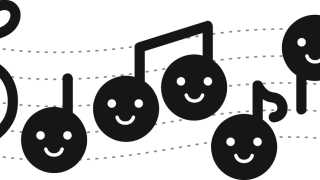

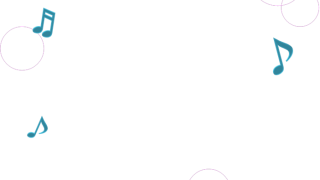
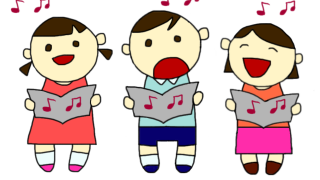







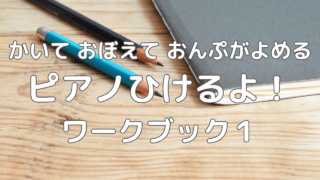



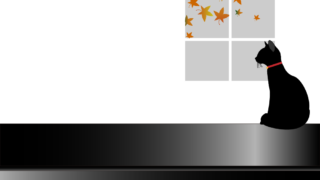

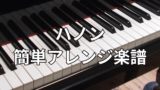

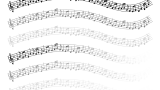
![全訳ハノンピアノ教本 (全音ピアノライブラリー) [ 平尾妙子 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0100/9784111040100_1_2.jpg?_ex=128x128)
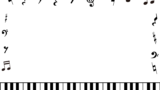
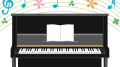

コメント
最近の風潮で、ハノンを弾かせない、と聞いてびっくりしています。ハノンは地味でつまらないので辛くて辞めてしまう(気持ちは分かるけど楽に上手くなんかなれないです)とか、黒鍵をあまり使わないから(何なんだ)みたいな理由みたいですね。
でも、ハノンがなかったら初心者のままではなかったか、ガクブル、、、。各指が独立して粒が揃い、どんな早さでもタッチをコントロールして弾けるようになる(これが出来れば、ある意味免許皆伝)には欠かせないです。ちゃんと使えば初心者を上級まで連れていってくれる教本です。私は高校生の時、課題以外にもランダムにどんどんページをめくり、毎日一時間ゆっくりから早く、弱く強く、付点や様々なメロディアクセントで、更に転調させてなど弾いてました。ハノン先生のコメントは奥深い。ハノン先生、生まれてくれてありがとうという感じですw
エンジェル様
コメントありがとうございます。
私もひたすらハノンをやってきた人間なので、「ハノンは必要ない」という考えを知ったときは「え~~!」でした。
エンジェルさんのおっしゃる通り、リズムを変えたりアクセントの位置を変えたり、転調したり・・いろいろ応用ができるよな、と思いますし、今のところは「やっぱり必要なんでは」という考えです。
「なぜ必要か」を考えるきっかけになったな、と思っていますが、「必要ない」という考えももっと深く知りたいな、とも思います。
はじめまして、コメント失礼致しますm(_ _)m
3歳〜17歳までピアノをやっておりました。(大学受験や大学生活の為に休んでいました)
ハノンの15まで終わっていたところでピアノを辞めたのですが、3年間のブランクってとても大きくて、現在ハノンの1、2をテンポ108までなら弾けるけれども左腕だけ疲れてしまうという状況です。。
右手は全く疲れません。
これって、左腕、左手の筋肉が足りないせいなのでしょうか?
それとも、本来抜くべき力が抜けていないのでしょうか?
るり様
コメントありがとうございます。
テンポ108で弾けるけれど、左手がとっても疲れてしまう、とのこと。
左手は右手と比べて動かしづらいし、疲れますよね。
分かります!
やはり余分な力が入ってしまっている、ということではないでしょうか。
あとは、弾くための腕の使い方などがうまくいっていない、ということもあるかもしれません。
ピアノを弾くには、筋力よりも筋肉の使い方が重要なようです。
右手は全く疲れない、ということなので、右手の弾き方を研究しつつ左手に置き換えるように練習してみてはいかがでしょうか?
参考になれば・・。