あまり子どもっぽくなくて、
でも初心者向けで、
よく知られた曲が多くて、
クラシックばかりではなくて・・
こんな曲集を探していて行き着いたのが、この『バイエル併用 ポピュラー・ピアノ曲集』。
「こどもから大人まで」というコンセプトのようで、大人の方も納得の選曲になっていると思います。
全2巻のこの曲集。1、2巻それぞれを詳しく紹介します。
⇩こんな人におすすめ!
『バイエル併用ポピュラー・ピアノ曲集』とは?
まずは、1,2巻通してどんな曲集かをまとめます。
『バイエル併用 ポピュラー・ピアノ曲集』は、2013年にドレミ楽譜出版社から出された全2巻の曲集です。
”バイエル併用”とある通り、バイエルをやっているくらいの人向け。
バイエルはピアノ導入教材なので、初心者向けということですね。
バイエルの対応番号は、以下のようになっています。
- 第1巻・・・バイエル20番~70番ぐらい
- 第2巻・・・バイエル70番~終わりぐらい
「はじめに」に以下のようにあります。
本書には、おとなにもこどもにも親しまれているファミリー・ソングの中から、より〈ポピュラー〉な曲が集められ、〔バイエル何番ぐらい〕というグレードに従ってやさしく編曲、配列されています。
『バイエル併用 ポピュラー・ピアノ曲集』「はじめに」より
「はじめに」には、
「子どもの通う教室に一緒に通う親の姿もあり、クラシック曲ばかりではなく知っている曲を気軽に楽しんでいる様子がある」
ということも書かれています。
そうしたことから、家族で使ってもらえるような曲集を作ったということのようですね。
スポンサーリンク
『バイエル併用ポピュラー・ピアノ曲集1』について

まずは、第1巻についてまとめます。
掲載曲は?
掲載されている曲はこちら↓です。(リンク先は演奏動画です)
バイエル20番から10番ずつに区切って、難易度順になっています。
- バイエル20~30番ぐらい
- 月の光に(フランス民謡)
- きらきら星(フランス民謡)
- バケツの穴(アメリカ民謡)
- ロンドン橋(イギリス民謡)
- ジャンバラヤ(ウィリアムス)
- ユー・アー・マイ・サンシャイン(デービス)
- 一週間(ロシア民謡)
- バイエル40~50番ぐらい
- はにゅうの宿(ビショップ)
- かわいいあのこ(インドネシア民謡)
- 旅愁(オードウェイ)
- 故郷の人々(フォスター)
- バロック・ホーダウン(ジャクエス&キングスレイ)
- ともしび(ロシア民謡)
- 愛のロマンス(スペイン民謡)
- 黒い瞳(ロシア民謡)
- 五月に(ベール)
- ケンタッキーの我が家(フォスター)
全44曲
どうでしょう。知っている曲が多いのではないでしょうか。
私も、知らない曲が少しありますがほとんどが知っている曲。
曲名を見ると、子どもより大人向けのような気がしますね。
関連記事→『バイエル併用ポピュラー・ピアノ曲集1』の掲載曲の一部を弾いてみました。
難易度は?
難易度については、「はじめに」に以下のように記されています。
第1集は〔バイエル前半ぐらい〕のため、ハ長調とイ短調という調号のない曲ばかりで、楽しいホームソングの他に、ビデオなどでおなじみの映画音楽や、ポール・モーリアなどのイージー・リスニング曲が弾けます。
『バイエル併用 ポピュラー・ピアノ曲集』「はじめに」より
すべての曲に調号はありません。
でも、臨時記号の付いている曲はあります。
- ローレライ
- バロック・ホーダウン
- ともしび
- 愛のロマンス
- 黒い瞳
- ケンタッキーの我が家
- 荒野のはてに
- おめでとうクリスマス
- 峠の我が家
- マイ・ボニー
- スカロボー・フェア
- クラリネットこわしちゃった
- レディース・ブルース
- 太陽がいっぱい
- エーデルワイス
- ともだちの歌
- ピアノ・オン・ザ・ロック
- ミッキーマウス・マーチ
- 不思議の国のアリス
- 右から2番目の星
- シェルブールの雨傘
- サバの女王
- 蒼いノクターン
- いつか王子さまが
全部で24曲。って半分じゃん!
有名な曲ばかりなだけあって、そう単純ではないということですね。
バイエル20番~30番
この曲集は、1番始めの「月の光に」からすべて両手奏です。
右手メロディー左手伴奏という形ですね。
右手のメロディーは、よく知られている曲ばかりなので弾きやすいと思います。
左手の伴奏は・・
4曲目「ロンドン橋」の後半が4分音符で動く形になりますが、それまでは2分音符や全音符になっています。
バイエル30~40番ぐらい
この「30~40番」では、8分音符や和音が登場します。
8分音符は、まずはメロディーに、そして、最後の曲で分散和音の形で伴奏に出てきます。
和音は、伴奏だけに出てきます。2和音→3和音の順ですね。
臨時記号も1か所だけあります。
バイエル40~50番ぐらい
これまでは、両手ともト音記号の楽譜でしたが、ここからヘ音記号が出てきます。
また、メロディーにも和音が登場します。
伴奏はだいぶ複雑になり、よく動くようになります。
2分音符などで伸ばすような形はあまり出てきません。
この章からリピート記号が登場し、曲が長くなります。
1カッコ2カッコやD.C.も出てきます。
バイエル50~60番ぐらい
伴奏はさらに複雑になってきます。
4分音符だけとか8分音符だけといった感じから、いろいろな音符が混じり、リズムが出てきます。
メロデイーも複雑になってきて、3連符や8分+16分のタッカのリズムが出てきます。
臨時記号も増え、1曲に何か所も出てくるようになります。
バイエル60~70番ぐらい
これまでよりも音域が広いという印象があります。
メロディー伴奏とも動きが大きいということですね。
一気に1オクターブ飛ぶことも、わりとしょっちゅうだったりします。
1曲の中で使われる音符が増え、より複雑になっています。
後ろに行けば行くほど、より曲らしい曲になっているといえるかもしれません。
楽譜はこんな感じ
実際の楽譜の様子もまとめます。
五線の幅は8㎜ほど。大きめではありますが、すごく大きいという感じではないですね。
1ページの段数は、始めのうち4段だったものが、終わりの方では5段になっています。
『バイエル併用ポピュラー・ピアノ曲集2』について

それでは、2巻に入ります。
収録曲は?
まずは、入っている曲についてです。(リンク先は演奏動画です)
こちらも70番から終わりまで10番ずつに区切られています。
- バイエル70~80番ぐらい
- 愛のよろこび(マルティーニ)
- 小さな木の実(ビゼー)
- さんぽ(となりのトトロより)(久石譲)
- 君をのせて(天空の城ラピュタより)(久石譲)
- オオカミなんかこわくない(チャーチル)
- 小さな世界(シャーマン兄弟)
- くまのぷーさん(シャーマン兄弟)
- ロミオとジュリエット(ロータ)
- バイエル80~90番ぐらい
- フニクリ・フニクラ(デンツァ)
- アニー・ローリー(スコット)
- ワルツィング・マチルダ(オーストラリア民謡)
- さらばジャマイカ(西インド諸島民謡)
- アロハ・オエ(リリウオカラニ)
- モルダウの流れ(スメタナ)
- 遠い日々(風の谷のナウシカより)(久石譲)
- 風の丘(魔女の宅急便より)(久石譲)
- 愛の夢 第3番(リスト)
- バイエル90~100番ぐらい
- アルハンブラの思い出(タルレガ)
- さらばナポリ(コットラウ)
- 愛のプレリュード(グノー)
- サウンド・オブ・ミュージック(ロジャーズ)
- ル・ローヌ(服部克久)
- 空をみあげて(黒人霊歌)
- ショパンのノクターン(ショパン)
- いつか夢で(眠れる森の美女より)(フェイン&ローレンス)
全33曲
こちらも有名な曲ばかり。
私もほとんど知っています。題名だけでは「?」という曲はありますが。
関連記事→『バイエル併用ポピュラー・ピアノ曲集2』の掲載曲の一部を弾いてみました。
難易度は?
バイエルは、すべて終えるとブルグミュラーへ進むのが一般的ですね。
なので、こちらの曲集も、終わりの方はほぼブルグミュラー程度の難しさといえるかと思います。
バイエル70番~がこの2巻になりますが、バイエル70番以降の特徴は調号が出てくることです。
調号なしの長短調(ハ長とイ短)、そして、♯4つまでと♭2つまでの長調がでてきますね。
そうしたことからか、この第2巻も調号が出てくるようになります。
とはいっても、♯、♭ともに1つまでで、圧倒的にハ長調が多いですね。
数えてみました。
- ♯1つ(ト長調)・・・6曲
- ♯1つ(ホ短調)・・・2曲
- ♭1つ(ヘ長調)・・・5曲
- ♭1つ(ニ短調)・・・なし
- 調号なし(ハ長調)・・・14曲
- 調号なし(イ短調)・・・4曲
- イ短→イ長(♯3つ)に転調・・1曲
- ハ長→ハ短(♭3つ)に転調・・・1曲
調号なしから同主調で転調して一気に調号3つになる、という曲が2曲ありますね。
1曲が長い
もう一つの特徴としては、第1巻と比べて1曲が長いということでしょうか。
ほとんどの曲が見開き2ページになり、さらにリピートする曲もあります。
1ページに収められている曲も8曲ありますが、ほとんどがリピートするようになっていますね。
難易度の差はあまりない
第2巻になると、始めの方の曲と終わりの方の曲の難易度はそれほどないように思います。
終わりへ行くほど多少難しくなっているかな。
”バイエルの70番以降のむずかしさ”ということになっていますが、70番から最後の106番までの主な特徴は
- 調号
- 16分音符が多い
- だんだん曲が長くなる
といったところかなと思います。
この『バイエル併用ポピュラー・ピアノ曲集2』でも調号は1曲目から出てきますし、曲も始めから長めです。
ただ、16分音符の頻度は全体的に少ないという印象ですね。
楽譜はこんな感じ
楽譜の様子もまとめます。
五線の幅は7㎜。第1巻よりは少し小さくなりますね。音符そのものも小さくなっています。
1ページの段数は、4段か5段で、これは変わりません。
『バイエル併用ポピュラー・ピアノ曲集』まとめ おとなの方のレパートリー集の1冊として
大人のピアノ初心者用の楽譜は、まだまだ少ないのが現状のような気がします。
そんな中、この『バイエル併用 ポピュラー・ピアノ曲集』は、バイエルの難易度で2冊に分かれ、様々な有名曲が入っています。

「大人向け」となっているものは、1冊でブルクミュラー程度まで入っているものが多い気がする・・
第1巻は始めから順番に、第2巻は好きな曲を選んで・・・
知っている曲を演奏する楽しみを感じられる曲集ではないかと思います。
また、「子どもから大人まで」がコンセプトのこの『曲集』。
1冊の中から家族で弾きあう、という楽しみ方もできるかもしれません。
レッスンでの副教材から発表会の選曲、自分や家族で楽しむため。
いろいろなシーンで使える曲集ではないでしょうか。
(公開日:2018年2月22日 最終更新日:2024年11月21日)
関連記事→『バイエル併用ポピュラー・ピアノ曲集1』の掲載曲の一部を弾いてみました。

→『バイエル併用ポピュラー・ピアノ曲集2』の掲載曲の一部を弾いてみました。

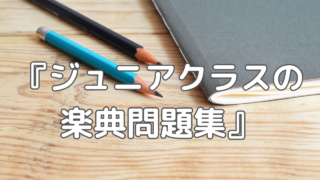

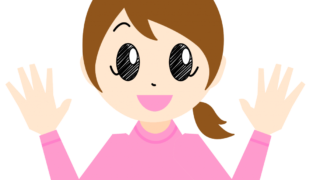



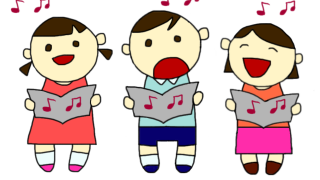




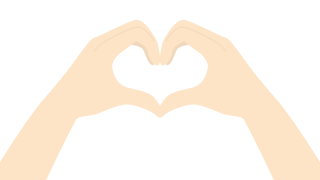

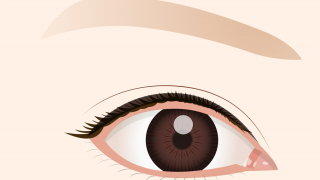

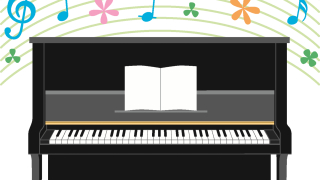
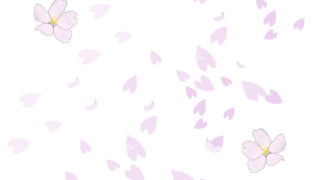

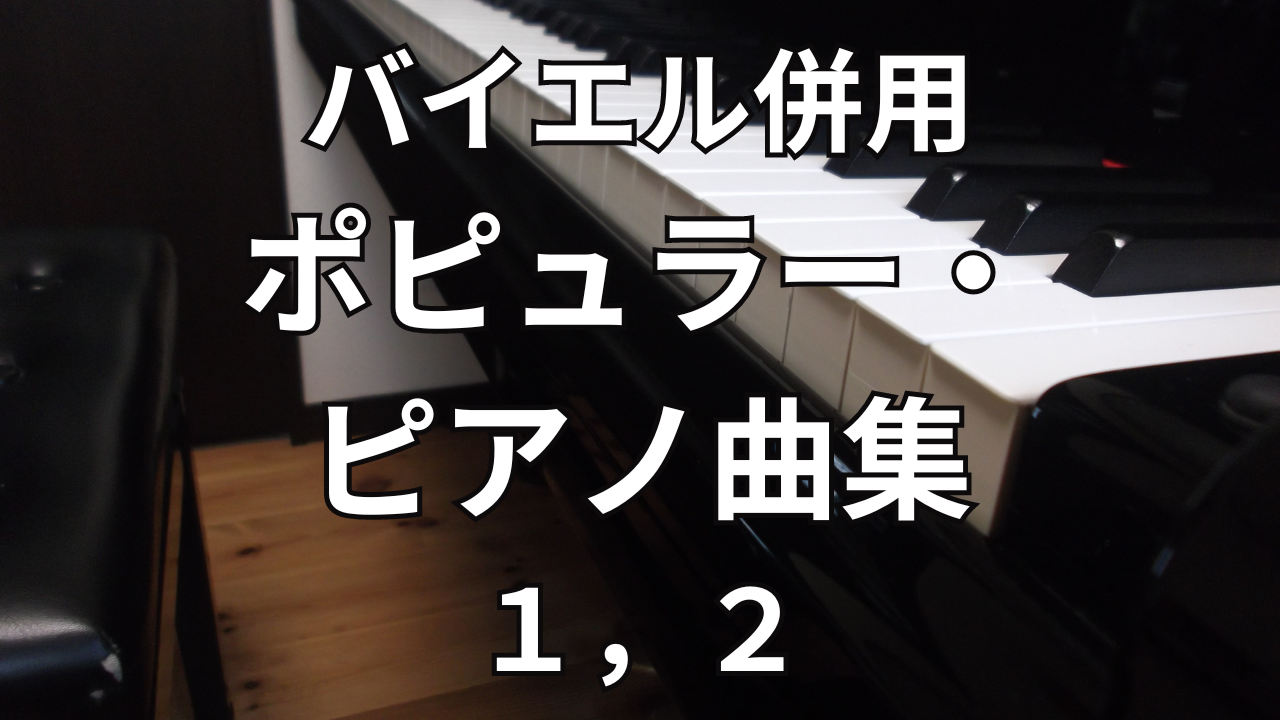






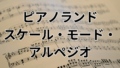
コメント