ピアノのレッスンは、曲を練習することとテクニックを身につけるための内容を、平行して行うことが一般的だと思います。
曲のテキストとは別に、テクニック用のテキストを使うことが多いですよね。
私の教室でも、基本的にそのようにしています。
でも・・
その、テクニック系のレッスンが好きじゃない、と思っている子、多いな・・という印象です。
あからさまに「え~、やりたくな~い」という子もいますし、はっきり言わなくてもイヤイヤだな・・と感じられる子も。
嫌がられていもやるわけですが・・それはなぜなのか。
私の考えをまとめてみます。
ピアノのテクニック教本ってどんな内容?
「テクニック教本」というのは・・
例えば、『バーナム ピアノ テクニック』や『ツェルニー〇番』や『ハノン』。
こういったテキストのことですね。
こうしたものを使ったレッスンを、曲のレッスンとともに並行して行うのが、ピアノのレッスンとしては一般的ではないかと思います。
文字通り、ピアノを弾くためのテクニックを身につけるためのレッスンということになります。
スラーやスタッカートや和音や、アルペジオやトリルや連符や・・
そうした内容に特化したことを、曲のレッスンとは分けて行います。
曲のレッスンとテクニックのレッスン、別に行うのはなぜ?
なぜ、曲のレッスンとは別にテクニックのレッスンを行うのか。
その理由は、次の3つに集約されるように思います。
- 曲の中に出てきたときに即対応できるように
- 手の形や動かし方等に集中できる
- 曲の仕上がりが早くなる
曲の中に出てきたときに即対応できるように
まずは、というか、最も大きな理由は、この「曲の中に出てきたときに即対応できるように」ということです。
スラーの弾き方、スタッカートの弾き方、和音の弾き方などなど・・
テクニックのテキストを通して日ごろから経験しておくことで、実際に曲の中に出てきたときにすぐに弾ける、ということです。
基本的な弾き方を身につけておくことで、曲の中に出てきたときに応用しやすくなります。
例えば、スタッカートの基本の弾き方を分かっていれば、曲の中で流れにふさわしい弾き方はどのようなものか、といったことに対応しやすくなります。
フォルテで弾き、なおかつ音が飛ぶ、などといった場合、力の入れ具合は?動かし方は?などといったことを行わなければいけません。
また、この曲にふさわしいスタッカートはどういうものか。柔らかい音か、弾む音か、いろいろな弾き分けも必要になってきます。
そういうことにすぐに注意を向けられる、そして、応用しやすいということです。
手の形や動かし方等に集中できる
テクニックのレッスンを別で行うことで、手の形や動かし方などにのみ集中して取り組むことができます。
これは、つまり「基本をしっかり身につけられるように」と言いかえることができると思います。
上にも書きましたが、実際の曲の中では、スタッカートはただ音を短くすればいいのではなく、その曲にふさわしいスタッカートを弾かなければいけません。
テクニックに特化した内容のレッスンの中で、手の形や動かし方等に集中して練習して基本の弾き方を身につけます。
そのうえで、それぞれの曲にふさわしい弾き方に応用する、ということですね。
曲の仕上がりが早くなる
曲とは別枠のレッスンで、基本の弾き方をしっかり身につけたうえで曲に取り組むので、曲の仕上がりは早くなります。
そうでなければ、スタッカートの弾き方そのものから練習しなくてはいけなくなります。
それでは効率が悪いですよね。
テクニックのテキストなどで、普段から様々な音形を何度も何度も経験しておくことで、さあ曲を弾こうとなった時に応用が利き、曲の仕上がりが早まる、ということです。
テクニック教本、イヤかもしれないけど・・
以前、レッスンに来ている子どもたちに年度末に合わせて「ピアノのレッスンの何が好き?何がイヤ?」といったアンケートを取っていました。
その際、「何がイヤ?」の欄に、必ず何人か「バーナム」と書く子がいます。

ハハ・・人気ないなあ(苦笑い)
一般的に曲っぽくないし(できるだけ曲らしいもので練習できるのが理想だと思います)、私も細かいことをいろいろと言いますし・・。
そのあたりが嫌がられる理由かな。
そして、そう書いた子には、「気持ちは受け止めた!でもやめないよ~~」と返事。
やる理由をきちんと話したり、曲と関係づけてレッスンしたり、こちらも工夫が必要と感じています。
イヤかもしれないけどやっぱり大事。
いろんな曲を弾けるようになりたいなら(結局はそこなのですが)、頑張ってほしいです!
(公開日:2018年5月22日 最終更新日:2025年1月28日)
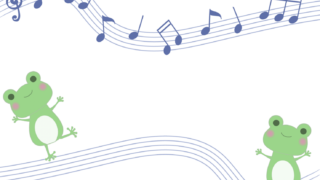
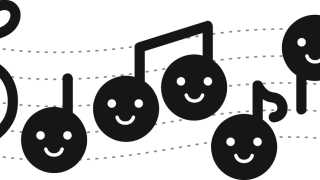

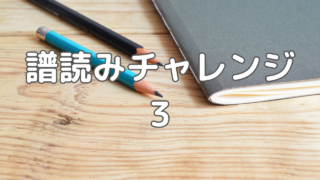
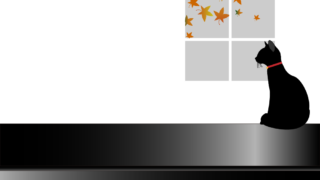

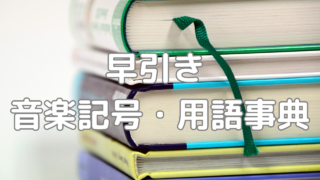

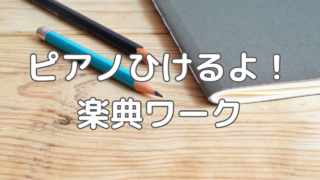



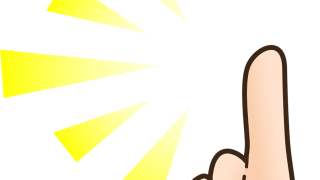
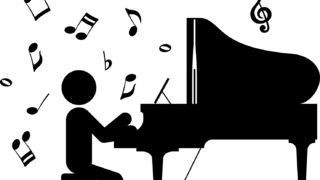







コメント