世界中で使われている、アメリカ発のピアノ教材『ピアノ・アドヴェンチャー』シリーズ。
2018年3月から、順次日本語版が出版されてきました。
今回は、シリーズの最初にあたる『はじめてのピアノ・アドヴェンチャー レッスン・ブックA』について、内容を詳しくまとめてみます。
とっても丁寧。しかも楽しく自然に音楽の世界へ入っていけそうな、そんなテキストです。
あわせて読みたい→『ピアノ・アドヴェンチャー 導入書』をこちらで紹介しています。
『ピアノ・アドヴェンチャー』シリーズって?
まずは、『ピアノ・アドヴェンチャー』シリーズそのものについてまとめます。
アメリカ発のこの教材。著者は、ナンシー・フェイバー、ランディー・フェイバー夫妻です。
アメリカのみならず、ドイツ、オランダ、中国、韓国など10の言語に翻訳されている世界的なピアノ教材ということです。
2018年から日本語版が順次出版され、2021年にすべてそろいました。
(併用教材「スケール&コードブック」1,2が2023年10月15日に発売されています。)
シリーズの構成は?
シリーズの構成は以下のようになっています。
- 『はじめてのピアノ・アドヴェンチャー』(4~6歳程度)
- レッスン・ブックA,B,C
- ライティング・ブック(ワークブック)A,B,C
- 『ピアノ・アドヴェンチャー』(6~11歳程度)
- レッスン&セオリー
- 導入書、レベル1、レベル2A,2B、レベル3、レベル4&5
- テクニック&パフォーマンス
- 導入書、レベル1、レベル2A,2B、レベル3、レベル4&5
- 併用教材 スケール&コードブック1,2
- レッスン&セオリー
テキストの進め方は・・
テキストを進めていく順番は、次のようになります。
4~6歳くらいの小さな子は『はじめてのピアノ・アドヴェンチャー』から始めます。
レッスン・ブックA、ライティング・ブックAから始め、順次Cまで進んだら、『ピアノ・アドヴェンチャー』レッスン&セオリーレベル1、テクニック&パフォーマンスレベル1へ入ります。
6~11歳くらいで始める場合は、『ピアノ・アドヴェンチャー』導入書からスタートです。
レッスン&セオリー導入書、テクニック&パフォーマンス導入書から始め、順次レベル4&5まで進んでいくということですね。
もちろんこれは目安。一人一人の状況によって違ってくると思います。
ともかく、
『はじめてのピアノ・アドヴェンチャー』レッスン・ブックA,B,Cの内容が、『ピアノ・アドヴェンチャー』レッスン&セオリー導入書の内容と同じ、
ということになりますね。
スポンサーリンク
他にもいろいろな楽譜が
メインテキストは以上のようになっていますが、他に様々な併用曲集があります。
私自身、「Level 2A」と書かれた英語版のクリスマス曲集を持っていて、裏表紙にはたくさんの曲集が紹介されています。
ClassicsやRock’n RollやJazz&BluesやPopularや・・
関連記事→『ピアノ・アドヴェンチャー』併用のクリスマス曲集についてこちらの記事の中で紹介しています。
参考→併用曲集など日本語版の無いものもこちらを通して購入することができます。
日本語版を出版した全音楽譜出版社が、正規輸入代理店となっています。
『はじめてのピアノ・アドヴェンチャー』の特長
まず、『はじめてのピアノ・アドヴェンチャー』全体の特長についてまとめます。
『はじめてのピアノ・アドヴェンチャー レッスン・ブックA』のはじめのページに以下のようにあります。
このメソードの指導理論は、フェイバー夫妻の提唱する”ACE”(「分析(Analysis)」「創造(Creativity)」「表現(Expression)」に基づいています。分析は理解に、創造は自己発見につながり、表現することは子ども達の芸術性を育てます。
『はじめてのピアノ・アドヴェンチャー レッスン・ブックA』「『はじめてのピアノ・アドヴェンチャー』について」より
また、特長として以下の4つが挙げられています。
①音楽の楽しさを発見する
②知覚能力の発達と音楽的テクニックの礎
③多様な音楽ジャンルに触れて、音楽性を高める
④付属CDで、これまでにないリスニング体験!
『はじめてのピアノ・アドヴェンチャー レッスン・ブックA』「『はじめてのピアノ・アドヴェンチャー』の特長」より
少し捕捉します。
①は、
「「遊び」の要素を多く採り入れた歌やアクティビティによって音楽の基礎を紹介します」
とあり、自然に楽しみながら音楽に触れていけるようになっているということですね。
②は、
「楽譜を「読む力(目)」や、音を「聴く力(耳)」などの知覚能力の発達を促します」
とあります。
また、
「即興などのカリキュラムによって創造力や豊かな感受性を育みます」
とあり、曲を演奏する力を初歩から身につけるようになっているということです。
③は、
「多様なスタイルの音楽を通して聴く力を養い、楽しみながら豊かな音楽性を身につけ、音楽性を高めます」
とあり、初歩から様々な音楽に触れられるようになっています。
④は、
「すばらしいオーケストレーションとヴォーカルによるCDが用意されており、これまでにないリスニング体験ができる教材である」
とあります。
CDはレッスン・ブックに付属されているのですぐに活用でき、豊かな音楽とともにレッスンや練習ができるということですね。(なお、日本語版は日本語の録音になっています)
『はじめてのピアノ・アドヴェンチャー レッスン・ブックA』の内容

前置きが長くなりました。
ここから『はじめてのピアノ・アドヴェンチャー レッスンブックA』の内容を詳しくまとめていきます。
この教材は、UNIT1~UNIT10に分かれています。
各UNITの内容は以下のようになっています。
目次をそのまま書き出します。
- ピアノに親しむ(座る位置/音の種類(小さい、大きい、長い、短い)/丸い手の形)
- 白鍵を弾く(指番号/しっかりとした指先/拍を揃える/上がる音・下がる音、同じ音の繰り返し)
- 黒鍵を弾く(リズムの模倣/腕の使いかた/しなやかな手首/2つの黒鍵)
- フォルテとピアノ(fとp/長調の音階/3つの黒鍵)
- 4分音符(4分音符の歌/ドレミの鍵盤)
- 2分音符(4分音符・2分音符の歌/ト音記号、ヘ音記号)
- 全音符(4分音符・2分音符・全音符の歌)
- 音の名前ードレミファソラシ(音の名前(白鍵)/ファ・ソ・ラ・シを使った歌/親指の位置)
- ドの5本指スケール(小節/ドの5本指スケールを使った歌)
- 五線の予習(大譜表(レッスン・ブックBへの準備)
以下に、各UNITごとにまとめてみます。
UNIT1に入る前に
UNIT1に入る前に、2ページ設けられています。内容は・・
- ピアノフレンズのしょうかい
- さあ、ぼうけんにいこう!
この教材に登場するキャラクターとして、5人の子どもたちとピアノの先生が紹介されていて、「きみと ピアノのぼうけんにいく ともだちだよ」と書かれています。
レッスンを「ピアノのぼうけん」と表現しています。
色々なページに登場して、一緒に学んでいくわけですね。
もう一人(1匹?)「ほたるのタップ」というキャラクターもいます。
次のページは「おんがくの「はく」ってなあに?」という副題がついています。
付属CDの曲に合わせて、拍をたたきながら歌うようになっています。
UNIT1 ピアノに親しむ
ここからいよいよ本題に入っていきます。
UNIT1は「ピアノに親しむ」。
「座る位置/音の種類(小さい、大きい、長い、短い)/丸い手の形」について学びます。
まずは、キャラクターの子どもたちがピアノを弾くように椅子に座っているイラストがあり、真似をして座ることでピアノを弾く姿勢になるようになっています。
いろんな場所の鍵盤を弾いて「ちいさなおと、おおきなおと、みじかいおと、なが~いおと」を出してみます。
それぞれの音を表現したイラストがあり、そこからイメージして音を出すんですね。
先生用の楽譜が2ページにわたって書かれていて、その演奏に合わせていろいろな音を弾いてみるようになっています。
これには、「れんだんで”そっきょうえんそう”」と書かれています。
手の形については、「まるいいしをもっているのをそうぞうして」形を作ります。
CDに合わせてごろんと落ちたり、つかんだり、回したりといった動きをやり、最後に鍵盤へ乗せます。
親指と人差し指で丸い形をつくり、その形のまま鍵盤を弾くということもします。
UNIT2 白鍵を弾く
UNIT2は「白鍵を弾く」。
「指番号/しっかりとした指先/拍を揃える/上がる音・下がる音/同じ指の繰り返し」という内容です。
まずは、番号の書かれたカラフルな指輪を各指につけているイラストがあり、CDの歌に合わせてそれぞれの指を動かしたりします。
そして、前のUNITで学んだ手の形で指を1本ずつ動かし、「しっかりとした指先」作りをします。
その際、「クッキーのやわらかいきじに、ゆびでチョコレートをおしこむのをそうぞうして」と書かれていて、CDに合わせて1本ずつトントントントンと動かします。
”まんなかのド”から左手で下がる音を、右手で上がる音を弾いていきます。白鍵を弾きます。
手は、1と3のゆびでつくった「どーなっつ」の形。「ちょっとだけミルクにつけるうごき」を「ちょんちょんちょんと手首をつかって」音を出します。
その形で「きらきらぼし」も弾きます。
どれも、CDや先生の伴奏に合わせて行います。
UNIT3 黒鍵を弾く
UNIT3は「黒鍵を弾く」です。「リズムの模倣/腕の使いかた/しなやかな手首/2つの黒鍵」という内容ですね。
まずは、「2つのこっけん」と「3つのこっけん」があることを学びます。
そして、黒鍵を使ってリズム模倣。
2つの黒鍵は2,3の指、3つの黒鍵は2,3,4の指を使って、左右とも行います。
腕や手首については、まず触って意識をすること。それから猫の動きをまねたり虹の曲線をイメージしたりして、動かしたり弾いたりします。
CDや先生の伴奏と一緒に、拍をそろえて弾くようにします。
UNIT4 フォルテとピアノ
UNIT4は「フォルテとピアノ」。「fとp/長調の音階/3つの黒鍵」について学びます。
ドレミファソラシドの音階を、フォルテとピアノで弾いてみることから始まります。
(音名についてはまだ学びません)
2と1の指で作った「ドーナッツのゆび」で弾きます。
イラストを見て、fとpどちらが合うかを考えて弾きます。
次に、2,3,4の指を使って3つの黒鍵の部分を弾きます。
クジラが潜っていったり虹が登っていったりするイメージで、弾く黒鍵の場所を次々変えていきます。
UNIT5 4分音符
UNIT5は「4分音符」。内容は「4分音符の歌/ドレミの鍵盤」となっています。
まずは4分音符をおぼえます。書くスペースもあります。棒が上の音符は右手、下の音符は左手と学びます。
そして、「はくをそろえてかんじる」というページがあり、先生の弾いた拍数の音符グループを指さしたり、拍をたたいてみたりします。
また、ここから五線の無いプレリーディング譜が登場し、それを見ながら黒鍵を弾きます。
楽譜に書かれた棒の向きを見て、どちらの手で弾くのかを考えて弾いていきます。
ここでリピート記号も登場します。
そのあと「ドレミ」が出てきます。
まずは、左は4,3,2、右は2,3,4の指で同時に弾きます。
鍵盤のイラストと同じ場所を弾くゲームをして、ドレミの場所や音名を覚えます。
そして、プレリーディング譜で書かれた曲も弾くようになっています。
UNIT6 2分音符
UNIT6のテーマは「2分音符」。「4分音符・2分音符の歌/ト音記号、ヘ音記号」という内容です。
まずは、2分音符をおぼえます。こちらも書いてみます。
次のページに、4分音符と2分音符の混じった音符グループが書かれています。
それを、自分で弾いたり(2と1の指のドーナッツで)先生が弾いたものを当てたりすることで、拍やリズムを学びます。
そして、ドレミの音のみを使う4分音符と2分音符の混じったプレリーディング譜を弾きます。
2曲ありますね。
最後に、ヘ音記号とト音記号が出てきます。
ヘ音記号は「ひだりてでひくひくいおと」、ト音記号は「みぎてでひくたかいおと」と学びます。
歌の歌詞で形をおぼえたり、動物の鳴き声でどちらかをイメージしたりします。
そして、ヘ音記号、ト音記号の付いたプレリーディング譜を弾きます。音は、ドレミのみです。
UNIT7 全音符
UNIT7は「全音符」。「4分音符・2分音符・全音符の歌」という内容です。
こちらもまずは全音符について覚えます。やはり書くスペースがあります。
そして、4分、2分、全音符の混じった音符グループが書かれていて、3と1の指のドーナッツで弾いてみたり、先生の弾いたものを当てたりします。
次に、3つの音符の入ったプレリーディング譜を弾きます。
左手は2,3の指で2つの黒鍵部分を、右手は2,3,4の指で3つの黒鍵部分を弾くようになっています。
2曲あります。
UNIT8 音の名前ードレミファソラシ
UNIT8は「音の名前ードレミファソラシ」です。
「音の名前(白鍵)/ファ・ソ・ラ・シを使った歌/親指の位置」という内容です。
まず、階段状になった線上に「ドレミファソラシ」と書かれたものがあります。
次のページには、7オクターブの音の名前の書かれた鍵盤のイラストがあります。
7オクターブ。つまり、ピアノの鍵盤そのものをイラストにしたということですね。
それを指さして名前を言ったり、”1と3のドーナッツの指”で名前を言いながら弾いたりします。
そして、黒鍵から白鍵の音を見つけるために、ドとファを左右交互に場所を変えてどんどん弾いていきます。
また、左手3,2右手2,3の指でファソラシを弾いていったりもします。
そして、ここで親指を使うことを学びます。
弾く際の親指の形も確認します。
曲が3曲あり、右手はファソラシを1,2,3,4の指で、左手はその下のドを1の指で弾きます。
(1曲は左手3,2でドレ、右手1,2,3でファソラを弾きます)。
このとき、右手1,4でファシと1,3の指でファラの重音を弾くところもあります。
最後に、CDや先生の伴奏に合わせて、先生の言った音を素早く弾く、というゲームもあります。
UNIT9 ドの5本指スケール
UNIT9「ドの5本指スケール」に入ります。内容は、「小節/ドの5本指スケールを使った歌」です。
まず、中央ドの1オクターブ下のドレミファソを左手5,4,3,2,1の指で弾きます。
そして、中央ドからドレミファソを右手1,2,3,4,5の指で弾きます。
UNIT1で学んだ手の形を思い出して弾くよう書かれています。
次に、小節について説明されています。
4拍ごとに区切るようになっています(つまり4/4拍子ですね)。
そして、小節線の加わったプレリーディング譜を弾きます。全部で4曲。
はじめの2曲は、右手4小節、左手4小節で全8小節。あとの2曲は全16小節で、左右の入れ替わりが多くなっていきます。
音は、どちらもドレミファソです。
UNIT10 五線の予習
最後のUNITです。テーマは「五線の予習」。内容は「大譜表(レッスン・ブックBへの準備)」となっています。
このUNITは2ページのみ。見開きでおおきな大譜表が書かれています。
左ページはヘ音記号の部分(中央ドから1オクターブ下のド)にドレミファソラシが。
右ページにはト音記号の部分(中央ド)にドレミファソラシドが書かれています。
「大譜表」や「五線」「線と間」という言葉を覚え、楽譜を指さしながら音の名前を言ったりします。
こちらはあくまで予習。これで終わりです。
この1冊でどこまで進む?~内容のまとめ~
ここまで、各UNITごとの内容をまとめてきました。
結局、この『はじめてのピアノ・アドヴェンチャー レッスン・ブックA』はどこまで進むのでしょう‥?
出てくる音符や記号、音域などは以下の通り。
- 音符:4分音符、2分音符、全音符
- 拍子:4/4拍子(拍子記号は学ばない)
- 記号:f、p、リピート記号、ト音記号、ヘ音記号、小節(線)、大譜表、五線、線と間
- 音域:左右ともにドレミファソ(右-中央ドから、左-中央ドの1オクターブ下)
- 弾く音:黒鍵→ドレミ→左ド右ファソラシ→左ドレ右ファソラ→左右ともドレミファソ
特長としては、次の様なことかと思います。
- 曲を弾く前に、手の形について丁寧に進められている。
- 「表現」をする事の最も基本となるフォルテとピアノがいち早く出てくる(UNIT4)。
- 曲らしい曲を弾くようになるのは、UNIT5で4分音符を学んで以降。
- 楽譜はすべてプレリーディング譜(5線の無い音の高低だけが示されているもの)。
- すべてのページで付属のCDを使うことができる。
なお、『はじめてのピアノ・アドヴェンチャー』は今回紹介した「レッスン・ブック」と「ライティング・ブック」があります。
「ライティング・ブック」はワークブックですね。
「レッスン・ブック」には「『ライティング・ブック』を活用しましょう」と書かれていて、各ページに対応ヵ所が記されています。
「レッスン・ブック」と「ライティング・ブック」はセット、ということですね。
付属CDについて
ここで、CDについて触れておきます。
『ピアノ・アドヴェンチャー』シリーズは、この『はじめての~~』も次の段階の『ピアノ・アドヴェンチャー』もすべてCD付きになっています。
(『ピアノ・アドヴェンチャー』レベル4&5にはついていません)
先生用伴奏の録音ではなく、リズム楽器を含む様々な楽器での演奏になっています。
『はじめての~~』の曲はすべて歌になっていますが、日本語版なので、ちゃんと日本語で歌われていますよ。
http://www.zen-on.co.jp/pianoadventure/listen_list/
『はじめてのピアノ・アドヴェンチャー レッスン・ブックA』楽譜の状況は?
ここで、紙面の様子を少し紹介します。
大きさは菊倍判の横長タイプです。
オールカラーのイラストで、色味のはっきりしたかわいらしい感じです。
専属キャラクター「ピアノフレンズ」がいたるところに登場します。
前述の通り、楽譜はすべて「プレリーディング譜」。
見開き2ページを使って、音の高低がわかりやすく示されている部分もあります。
UNIT6でト音記号、ヘ音記号を学びます。そこまでは楽譜にも書かれません。
小節線を学ぶのはUNIT9。そこから小節線で区切られた楽譜になります。
先生用の楽譜は基本的に下に小さめ載っています。
生徒が先生の弾く音に合わせて自由に弾く、という場合は、全面が先生用の楽譜になっています。
参考→こちらからサンプルページを見ることができます。(下の方)
『はじめてのピアノ・アドヴェンチャー レッスン・ブックA』まとめ ゆっくり丁寧に そして楽しく
対象年齢が4歳~ということで、とにかく進み方はゆっくりで丁寧ですよね。
イラストも豊富で見た目も楽しい雰囲気。
特定のキャラクターがいるというのも親しみがわくかもしれません。
文章表現も、
「みぎての3-1のゆびでつくったドーナッツを、ちょっとだけミルクをつけるうごき」
とか、
手の形をつくる際には、
「きれいなまるいいし」「きみの(いしの)いろはなにいろ?」「まほうのいし」
といった書き方になっていて、興味を持ってもらいやすい工夫を感じます。
また、一度学んだことが何度も出てきて、その都度思い出すように促されています。
行きつ戻りつ、繰り返しつつ進んでいくことが大切にされています。
小さな子にはピッタリ。楽しく分かりやすくレッスンを進められそうです。
(公開日:2018年7月12日 最終更新日:2024年3月27日)


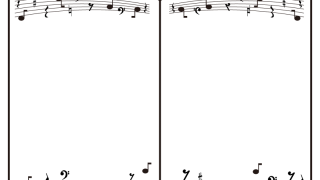




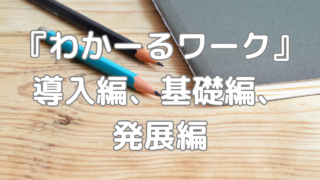
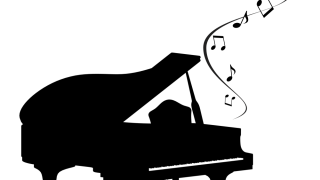
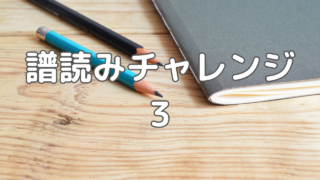

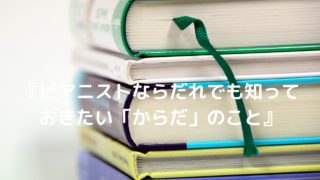
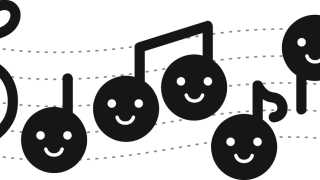


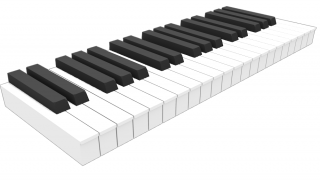
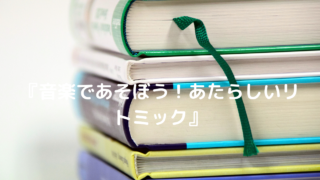

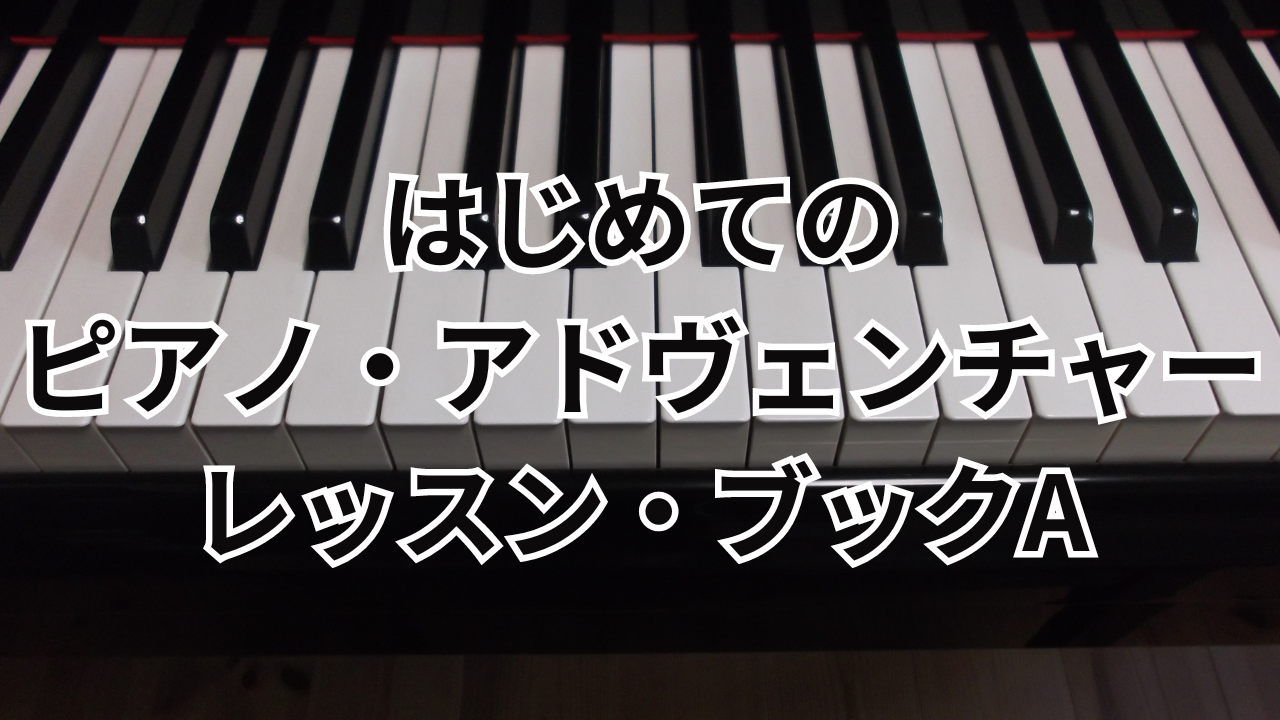

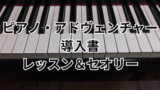



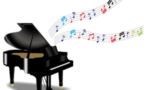
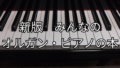
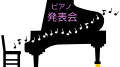
コメント