ピアノを弾くとき、手首が下がってしまう子は多いですね。
大人もかな。
はじめはわりといい形で弾いていたのに、だんだん下がってきてしまう・・ということも。
手首が下がった状態は、ピアノを弾くフォームとしては良くないです!
⇩それはなぜか?
では、手首が下がらないようにするにはどうすればいいのでしょう?
私は、「肩」を意識することだと考えています。
手首が下がる2つの原因
私が、ピアノを弾くときに手首が下がってしまう原因として思い当たるのは、次の2つです。
- 行き過ぎた脱力が手首を下げる
- 指だけを動かしてピアノを弾いている
行き過ぎた脱力が手首を下げる
ピアノを弾くときには「脱力」が大事!とよく言われます。
それは、”余分な”力を入れないということ。完全に力を抜いてしまってはピアノは弾けません。
手首が下がらないようにするためには、そのための力が必要です。
必要な力も抜いてしまう”行き過ぎた脱力”が、1つの原因ではないかと考えています。
力を抜きすぎてしまうと、鍵盤に指でぶら下がるような状態で弾くことになります。
それは、手首が下がった状態ですね。
指だけを動かしてピアノを弾いている
ピアノは、一見すると指だけを細かく動かして弾いているように見えます。
でも、実際は体全体を連携させて弾いています。
そのことがうまく体感できていないと指だけを動かして弾くことになり、手首の力は必要なくなり下がっていきます。
これが、子どもによく見られる状態ではないかと感じています。
ピアノを始めたばかりのころは、5本の指のみでおさまるような狭い音域を弾きます。
そのため、体全体を大きく動かす必要はなく、指を動かすだけで弾けてしまいます。
はじめのうちは、ピアノの鍵盤が重いので腕などの力も借りながら弾くことになり、手首もいい位置に保たれていることが多いですね。
でも、慣れてきて音を出すことに苦労しなくなると、だんだん指だけで弾くようになります。
そして、手首が下がります。
指の動かし方も、高く振り上げて打ち下ろすような形になりがちです。
これも、本来の弾き方ではないですよね。
手首が下がらないようにするためのフォームの作り方と指の動かし方
では、どうすればいいのでしょう?
ピアノを弾くフォームを作るには、「肩」がとても大切です。
手を鍵盤の上に乗せるとき、肩から動かします。
「肩」を意識したフォームの作り方
ピアノを弾くときのフォームの作り方は、次のようにします。
(参照:『ピアニストならだれでも知っておきたい「からだ」のこと』〔春秋社〕p.91より)
- 腕をだらんと下へ下げる
- 手の甲を上げるイメージで腕を上げて鍵盤の上に下ろす
まず、肩の力をしっかりと抜いて、腕を完全にだらんとさせます。
しっかりと力が抜けていれば、手のひらは斜め後ろを向くはずです。
指も、軽く内側に曲がります。
その状態から、手の甲を上にして上げていきます。
その時に、肩から動かすことを意識します。
そして、鍵盤の上に指が軽くついているような状態に手をもっていきます。
その状態を保ったまま弾きます。そうすれば、手首が下がらず弾くことができます。
この状態を保つためには、そのための力が必要です。
これは、”余分な力”ではありません。
参考記事→こちらで書籍の紹介をしています。
指の動かし方
ピアノを弾くとき、指はそのまま鍵盤を押し下げます。
先に記した方法で鍵盤の上に指を乗せたら、そのまま下げる、ということです。
指を高く持ち上げて振り下ろすような形ではありません。
そのまま下げる弾き方をするためには、肩から腕にかけての力が必要です。
肩から腕にかけてのしなりを活かして弾くということです。
私は、
音を出すための力が、肩から腕、そして指を通って鍵盤へ流れていく
というイメージで考えています。
あくまでも私のイメージですが。
指だけの力で弾こうとすると、指を上から振り下ろして、さらに押さえつけるような弾き方になる。
それを楽にしようとすると手首が下がる。
そういうこともあるのではないかな、と考えています。
肩から腕にかけての力を使ってフォームを保ち、その力を鍵盤へ流すイメージで弾く。
そんな風に考えると、手首が下がることなく弾けるのではないでしょうか。
手首が下がっていない状態を体験するために
自分の教室のレッスンに来ている子に「手首を上げよう!」と話すと、手首だけをぴょこんと上げることが多いですね。
手首のことだけを伝えると、そりゃあそうなるよな・・という感じです。
肩から腕全体を意識してもらうにはどうすればいいのか・・
2つ方法をご紹介します。
- 黒鍵を弾くときの手の形を作ってもらう
- アルペジオを弾く
黒鍵を弾くときの手の形を作ってもらう
1つは、黒鍵を弾いてもらうということです。
黒鍵を弾くためには、手を鍵盤の奥へ持っていく必要があります。
そうすると、必然的に手首は上がります。上げないと弾けないから。
普段手首が下がっている子も、黒鍵を弾かなければいけない時は上がるんですよね。
なので、意識的にその状況を作り、
手首を上げるってこういうこと!
と、しっかりと認識してもらうということです。
その時に、
肩や腕で上げるんだよ!
と、弾くときに必要なのは手や指だけではない、ということも併せて伝えるようにします。
アルペジオを弾く
もう1つは、アルペジオを弾くことです。
アルペジオは広い音域を弾くことになります。
1オクターブの範囲のアルペジオを弾く場合でも、指を大きく開かなければいけません。
手首が下がっている状態では弾きにくいはず。
やはり、普段よりも上げて弾こうとするんですよね。
指くぐりをしてさらに広い音域を弾くとなると、腕や肩を意識せざるを得なくなります。
そうした音域をあえて弾いてもらうことで、手首の位置の重要さを伝えていきます。
関連記事⇩指くぐりについてこちらの記事にもまとめています。
まとめ
ピアノを弾くとき手首が下がらないようにするために、弾くときのフォームの作り方、腕や肩を意識してもらう方法をまとめてきました。
私がレッスンをする中で体験したこと、感じたことを書いてみました。
手首が下がった弾き方がなぜマズイのか、下がらない弾き方をするには何をどうすればいいのか。
しっかりと体験してもらうことが大切では、と思っています。
形だけ正そうとしても、手首だけがぴょこんと上がってしまうだけなんですよね。
どうしたもんかな・・と考えて、今に至っています。
何か役に立つ部分があればうれしいです。
⇩ピアノの弾き方の基本や指くぐりについてまとめています。
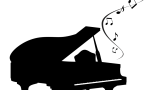



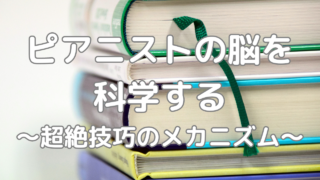
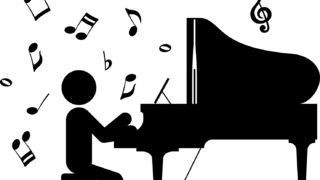



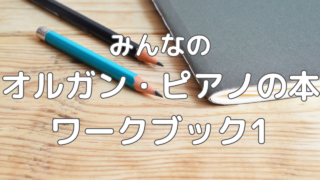

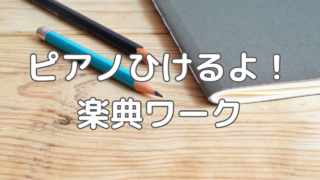
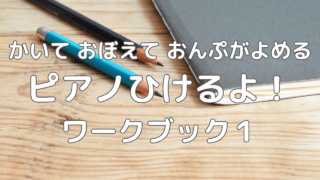
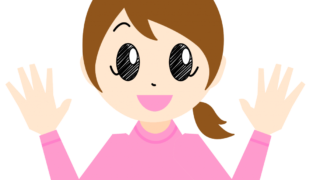


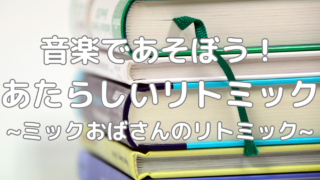



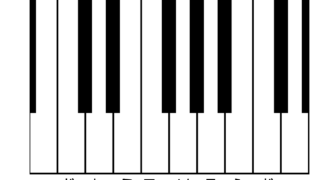

![ピアニストならだれでも知っておきたい「からだ」のこと [ トーマス・マーク ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5057/9784393935057.jpg?_ex=128x128)
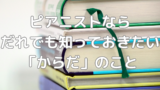


コメント