4つの教本比較表
ここまで4冊の教本について両手奏の進み方をまとめてきました。
内容を以下の項目で表にしてみました。
- 特徴
- 両手奏の始まる場所
- 両手奏の最初の左手の形
- 左の二和音初登場
- 左の三和音初登場
| 教本名 | 特徴 | 両手奏の始まる場所 | 両手奏での左右の役割 | 両手奏の最初の左手の形 | 左の二和音初登場 | 左の三和音初登場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 『ピアノランド』 | 様々な形が混在 | 1巻の最後から2曲目のみ | 左手は典型的な伴奏形ではない | 1小節に2音 ・8小節中2小節 ・音変わる | 2巻最後の曲 ・5度音程の二和音 ・曲全体で1小節伸ばす形 | 3巻最後の曲 ・ミソシ、レファシ、ドミソの和音をのばす形で各1小節ずつ |
| 『ピアノひけるよ!ジュニア』 | 左手をどんどん動かす | 2巻の後半から | 基本的に右手メロディー左手伴奏 | 両手ユニゾン ・8小節すべて ・ドレミファソの5音 ・4分音符で動く形が主 | 3巻中ごろ ・3度音程の二和音 ・1小節のみ ・4分音符2つ+2分音符のリズム | 3巻までは無し(『ピアノひけるよ!シニア』1巻以降) |
| 『ぴあのどりーむ』 | 和音を多用し同時に調性も学ぶ | 2巻の後半から | 右手メロディー左手伴奏 | メロデイーと同じリズム ・8小節中2小節 ・2分音符4分音符2つのリズム+1小節伸ばす ・すべて同じ音 | 3巻の前半 ・曲全体で2度、5度音程の二和音 ・1小節伸ばす形 | 4巻前半 ・1曲の中でⅠ Ⅴ7の和音 ・曲の前に「ハ長調の音階」を学ぶ |
| 『オルガン・ピアノの本』 | 様々な両手奏の形を順序だてて学ぶ | 1巻の後半から | 基本的に右手メロディー左手伴奏 | メロディーと同じリズム ・8小節中の2小節ずつに分かれて計4小節 ・すべて4分音符4分音符2分音符のリズム ・すべて同じ音 | 1巻の後半 ・曲全体で5度音程の二和音 ・1小節伸ばす形 | 2巻の前半 ・ドミソの和音 ・曲の最後に1か所のみ ・2分音符 |
| 教本名 | 特徴 | 両手奏の始まる場所 | 両手奏での左右の役割 | 両手奏の最初の左手の形 | 左の二和音初登場 | 左の三和音初登場 |
両手奏初登場はいつ?
一番早く両手奏が始まるのは、『オルガン・ピアノの本』ですね。
1巻の後半に入ったところで、メロディーと同じリズムを弾く形で登場します。
そして、それ以降の曲はすべて両手奏になります。
一方、始まるのが遅いのは『ピアノひけるよ!ジュニア』と『ぴあのどりーむ』で、ともに2巻の後半に入ったところです。
もう少し細かく見ると、2巻全体から見て『ピアノひけるよ!ジュニア』は前半の最後、『ぴあのどりーむ』は後半に入ったはじめの方といったところ。
『ぴあのどりーむ』が一番遅いといえそうです。
『ピアノひけるよ!ジュニア』はその後はすべて両手奏になります。
一方『ぴあのどりーむ』は、3巻の初めまで両手でメロディーを弾き継ぐ形の曲を挟みながら進んでいきます。
『ピアノランド』は、1巻の最後から2番目の曲で初めて両手同時に弾く部分があります。
1巻の最後の曲は左右で弾き継ぐ形になっていて、2巻に入っても時々その形の曲が出てきます。
両手奏はどんな形から始まる?
初めて両手奏で弾く場合の左手の状態について、もっともよく動かす形になっているのは『ピアノひけるよ!ジュニア』ですね。
8小節を両手ユニゾンで弾くようになっていて、8小節のほとんどが4分音符で動く形になっています。
これは、曲というより「ドレミファソ」を両手で弾く“練習”といった状況です。
他の教本は、8小節中の2小節程度の両手奏で、すべて同じ音で4分音符と2分音符程度のリズムで弾く場合が多くなっています。
両手奏での左右の役割は?
両手奏について考えるとき、左右の手の役割がどうなっているのかは重要ではないかなと思います。
その辺りがどうなっているかというと・・。
基本的にはどの教本も「右手メロディー左手伴奏」という役割分担になっています。
特徴的なのは、『ピアノランド』です。典型的な左右の役割分担にはなっていません。
左手メロディーがあったり、隣り合った音で移動していたり、並行奏のような形があったりと様々な動きをしています。
両手奏が始まったばかりの2巻では、1曲の中のごく一部分だったり、同じ音や同じリズムが続いたりという形です。
3巻になると音の数も増え、1曲の中で様々な形が混ざり、かなり複雑になっています。
もう1つ特徴的なのは、『ピアノひけるよ!ジュニア』かと思います。
基本的に「右手メロディー左手伴奏」ではありますが、3巻に入ると少しずつ1曲の中で対旋律のような動きが混ざるようになります。
つまり、左もメロディーのように動くということですね。
4分音符で「ド↗ソ ド↗ソ」といった一般的な伴奏形の部分もあり、メロディーのように動く部分もありと、左右が常に動く形になります。
『オルガン・ピアノの本』では、「2声のための練習」という項目があり、左右ともにメロディーのように動く練習の曲とはっきり位置付けられています。
もっとも明確に「右手メロディー左手伴奏」となっているのは、『ぴあのどりーむ』ですね。
少なくとも4巻までは、他の教本のような複雑な両手奏は出てきません。
和音の状況は?調性については?
和音を弾くことは、少し難易度高目の状況になりますね。
また、調性へつながることでもあるので、どのような使われ方をされるのかは重要かと思います。
和音の登場が最も早いのは『オルガン・ピアノの本』ですね。
1巻の後半で両手奏になってすぐ、5度音程の二和音(ハ長調の曲でド↗ソ)の形で出てきます。
2巻では、同時に弾く形を含みつつ分散和音が順次出てくるという状況になり、最後にハ長調音階を学びます。
特徴的なのは『ぴあのどりーむ』ですね。
3巻で二和音、4巻で三和音と和音が出てくるのは比較的遅いですが、和音が出てきてから左の伴奏は和音がとても多くなります。
4巻の前半でハ長調の音階を学び、それ以降は分散和音の伴奏が増えます。
ハ長調の曲がほとんどで、主要三和音のみが使われています。
もう一つ特徴的なのは、『ピアノひけるよ!ジュニア』です。3巻までに三和音の登場はなく、調性の説明もありません。
二和音は3巻で初めて出てきます。ド↗ミということで、ハ長調のⅠの和音ですね。
ハ長調の曲で、4分音符で「ド↗ソ ド↗ソ」や「シ↗ソ シ↗ソ」「シ↗ソ ファ↗ソ」と弾く、という形は3巻のはじめから出てきます。
これは、分散和音といえますね。
『ピアノランド』については、典型的な伴奏ではないので、和音についても様々な形で登場します。
主要三和音以外の音も多く使われています。
三和音は3巻の最後になって初めて出てきます。
まとめ
『ピアノランド』『ピアノひけるよ!ジュニア』『ぴあのどりーむ』『オルガン・ピアノの本』の4つの教本の、両手奏の進み方についてまとめてきました。
それぞれ違いがあり、選ぶ際にはますます悩んでしまいそうです。
曲を大いに楽しむ『ピアノランド』。
両手をしっかりと動かす『ピアノひけるよ!ジュニア』
調性感覚を大切にする『ぴあのどりーむ』。
順序だてて伴奏形を学ぶ『オルガン・ピアノの本』。
一言でいうと、こんな感じでしょうか?
今回は「両手奏」がテーマでしたが、他の部分でもそれぞれ特徴がありますし、使う子どもの状況によっても、合う、合わないがあるかと思います。
それぞれの特徴を理解して、総合的な判断が必要になりますね。

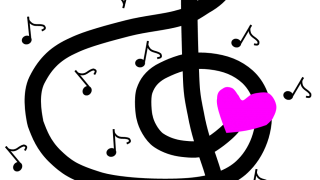


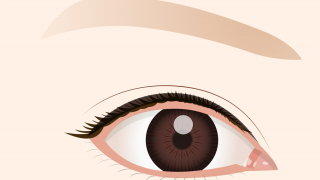


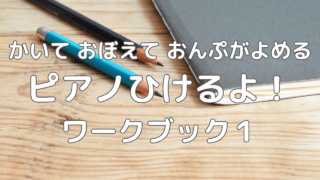






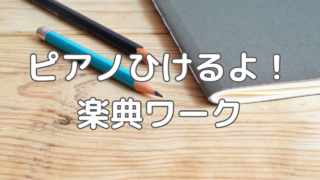

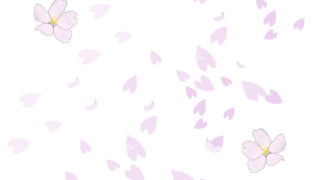

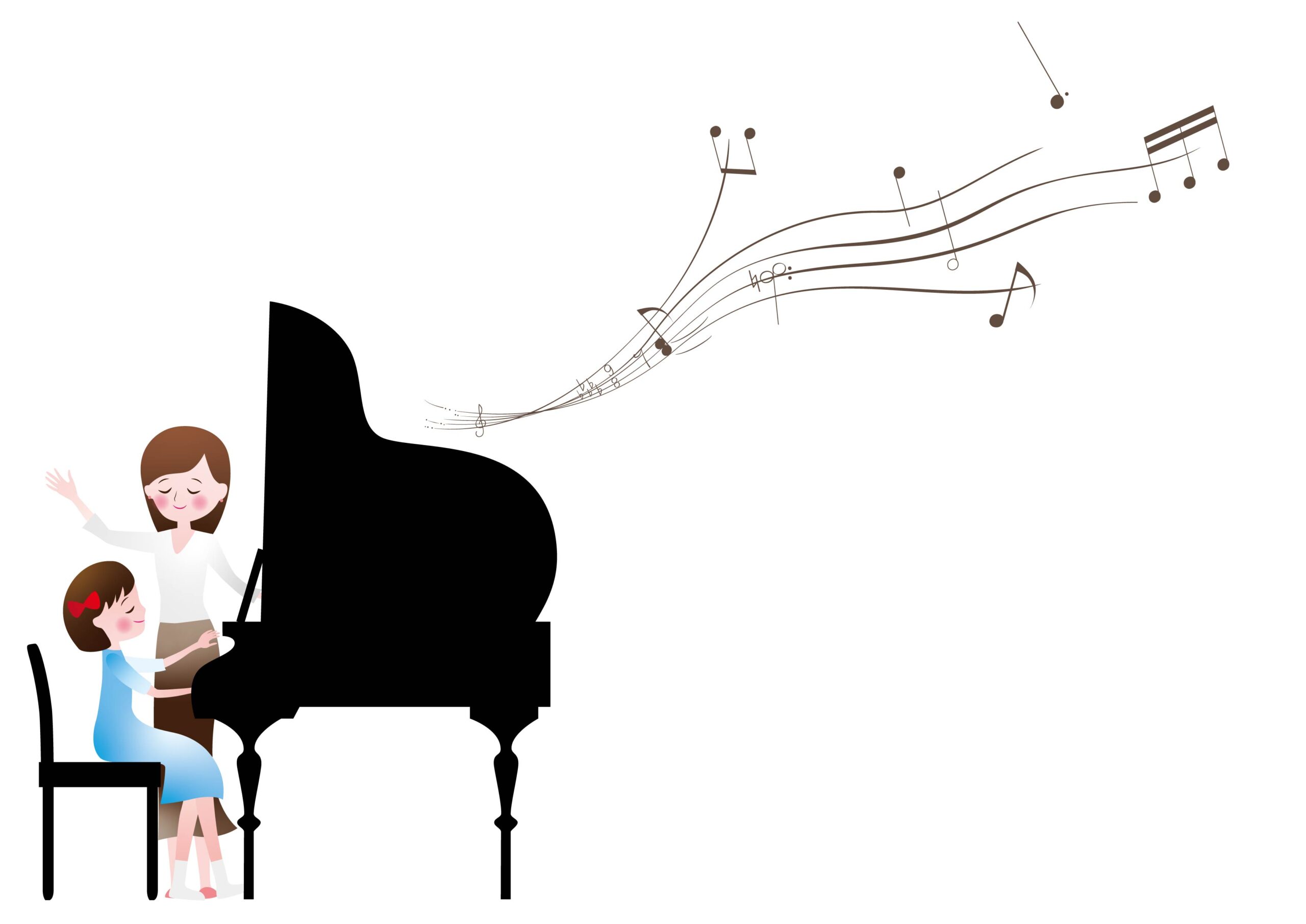
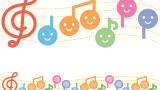
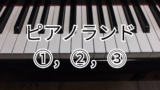
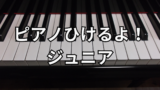
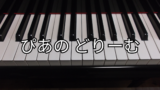
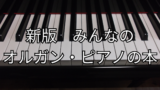


コメント