『おとなのためのピアノ教本』と『シニア・ピアノ教本』。
どちらも大人向けピアノ導入教本です。
でもこの2つはちょっと違い、
『おとなのためのピアノ教本』を簡単にしたものが『シニア・ピアノ教本』
という位置づけで作られています。
当ブログでも
- 『おとなのためのピアノ教本』・・・ちょっと経験のある人向け
- 『シニア・ピアノ教本』・・・全くの初心者向け
として、内容を紹介しました。
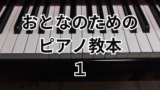
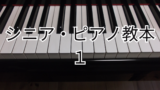
今回は、もう少し具体的に、どこがどういう風に違うのかをまとめてみようと思います。
『シニア・ピアノ教本』は導入部分のみ

『おとなのためのピアノ教本』を簡単にしたものが『シニア・ピアノ教本』
と上に書きましたが、『シニア・ピアノ教本』の「はじめに」に以下のようにあります。
すでに定評をいただいている拙著「おとなのためのピアノ教本」全5巻の導入部分を、よりやさしく、どなたにも無理なく進めるように改編したものです。
『シニア・ピアノ教本』「はじめに」より
ピアノの導入部分というと、一般的にはバイエル終了くらいまで。
『おとなのためのピアノ教本』は、第4巻まででソナチネ・アルバム程度まで進むとされています(5巻はソナチネ~ソナタ・アルバム程度の曲集です)。
なので、「バイエル終了」というと第2巻までになりますね。
ということは、
となりますね。
『おとなのためのピアノ教本』で第2巻までで終わらせている内容を、『シニア・ピアノ教本』では全3巻にわたって書かれているということです。
詳細記事→『おとなのためのピアノ教本』をこちらで詳しく紹介しています。
詳細記事→『シニア・ピアノ教本』をこちらで詳しく紹介しています。
スポンサーリンク
『おとなのためのピアノ教本』『シニア・ピアノ教本』進み方はどう違う?

『おとなのためのピアノ教本』1、2巻分の内容を『シニア・ピアノ教本』3巻に分けて、ということは、進み方がゆっくりだということですね。
具体的に何がどう違うのか、以下の5つの視点でまとめてみます。
1曲目に入るまでが違う
『おとなのためのピアノ教本』、『シニア・ピアノ教本』のどちらも、1曲目に入るまでにピアノの鍵盤や楽譜の読み方など、基本的な事柄が抑えられています。
でもやっぱり『シニア・ピアノ教本』の方が少し丁寧ですね。
どのへんが・・?
- 図や写真が少し多い
- 説明文が少し丁寧
- 楽譜や文字が大きめ
こんなところでしょうか。
例えば・・・
【鍵盤の説明】
- 『おとなのためのピアノ教本』は鍵盤の写真
- 『シニア・ピアノ教本』は、鍵盤の図
図の方がコントラストがはっきりしていて分かりやすいですね。
【弾くときの手の形】
- 『おとなのためのピアノ教本』は良い形の写真1枚
- 『シニア・ピアノ教本』は良い形+良くない形の写真2枚
そして、『シニア・ピアノ教本』は、文字や楽譜が全体的に大きめです。
そのため、『おとなのためのピアノ教本』では5ページに収められている内容が、『シニア・ピアノ教本』では6ページになっています。
また、紙質も違えているようです。
『シニア・ピアノ教本』は真っ白なのに対して、『おとなのためのピアノ教本』は少し黄色っぽい感じです。
こういうことも、見やすさに大きく関係してくるのではないかな。
音域の広がり方が違う
ピアノの導入の際に重要なことの1つに「音域の広がり方」が挙げられると思います。
これが、2つで大きく違っています。
まとめると以下の通り。
音域の広がり方は以上のようになっています。
『おとなのためのピアノ教本』は「中央ドから上下に広がる」形ではありません。
右は中央ドからドレミ。左は右の1オクターブ下のミファソから始まります。
一方『シニア・ピアノ教本』は、「中央ドから上下に広がる」形です。
右は中央ドからドレミ、左は中央ドからドシラでスタートです。
そして、『おとなのためのピアノ教本』はすぐに5指を使います。
『シニア・ピアノ教本』では1つづつ増えていきますね。
『おとなのためのピアノ教本』は、まず5指で調の始めの5音のみを弾き、2巻に入ると左右とも指くぐりをして、各調の音階を両手で弾くことで音域をひろげます。
『シニア・ピアノ教本』は、5指を使うようになるとメロディーを弾く右手のみ指替えや指くぐりをして音域をひろげていきます。
左はコードを弾くことが基本で、調が変わるとともに5指を移動させていく、という形をとっています。
両手弾きの進め方が違う

ピアノは、基本的に両手で弾くものです。
どのようにこの「両手弾き」へ進めていくのか。ここも少し違っています。
両手弾きへの進め方は上のような状況です。
大きく違うのは1ですね。
『おとなのためのピアノ教本』はすぐに両手とも5指を使うようになり、同時に左右それぞれでメロディーを弾きます。
しかも、それも1,2曲弾いたらすぐに右メロディー左伴奏になります。
ただ、「新しい調にはいったらまずは両手ユニゾンを」という形になっていて、両手ユニゾンは2巻に入っても行います。
『シニア・ピアノ教本』は、左右とも5指まで広がり、左手が中央ドの1オクターブ下のドレミファソへ移動したら「両手ユニゾン」が始まります。
(その直前に左のみでメロディーを弾く曲が1曲あります。)
それまでは、左右でメロディーを受け渡す形で弾くことになりますね。
コードを弾く進み方が違う
もう1つ違っているのは、コードの弾き方です。
どちらも左の伴奏はコードを弾いていくことになりますが、この進み方です。
コードの進み方は以上のようになっています。
『おとなのためのピアノ教本』は、まずは単音でハ長調の主音と属音(ドとソ)のみで弾くことから始まり、すぐに三和音になります。
一方『シニア・ピアノ教本』は、単音⇒重音⇒重音分散⇒三和音という流れで、三和音に入るまでが長いですね。
もう一つの違いは、『おとなのためのピアノ教本』にはコードネームだけを見て弾く、という伴奏づけの課題が載っていることです。
曲の左手で弾く部分で音符の書かれていないところがあり、そこを弾いていくという形です。
これは2巻に入っても続きます。
また、調の進み方も違っています。
『おとなのためのピアノ教本』は、まずは長調。その後同じ調号を持つ短調、という順に進みます。
『シニア・ピアノ教本』は、同じ調号を持つ長調と短調を続けて学ぶ、ということですね。
さらに、『おとなのためのピアノ教本』では「ベースライン」の項目が3つに分けて設けられています(2巻)。
これは、ただ和音を弾くだけではなく、ベースの音だけを弾いたり、ベース音とコードを交互に弾いたりといった、伴奏のいろいろな弾き方を示したものです。
この項目では、分数コードも出てきます。
出てくる調についてはどちらの教本も同じです。♯♭ひとつづつまでということですね。
その他の違い
出てくる拍子や音符の種類、楽譜の記号などは、多少出てくる順番が前後したりしていますが、大きな違いはありません。
『シニア・ピアノ教本』では2回に分けて説明されていたり、1項目設けられていたり、ということはあります。
例えば、タイやリピート記号、強弱記号などは、『おとなのためのピアノ教本』では特に項目を設けての説明はありません。出てきたときにひと言説明されているのみです。
また、シンコペーションについて『シニア・ピアノ教本』には項目を設けて説明がありますが、『おとなのためのピアノ教本』にはありません。
それぞれについてまとめて見ます。
- 出てくる拍子
- 4/4拍子、3/4拍子、2/4拍子、2/2拍子、6/8拍子
- 出てくる音符
- 4分音符、2分音符、全音符、付点2分音符、付点4分音符、8分音符、16分音符、3連符、装飾音符
- 出てくるリズム
- 付点4分+8分(タ~ンカのリズム)、付点8分+16分(タッカのリズム)
- シンコペーション(『シニア・ピアノ教本』のみ)
やっぱりちょっと難しい『おとなのためのピアノ教本』
『おとなのためのピアノ教本』1,2巻とその簡単版である『シニア・ピアノ教本』1~3巻を比べてみました。
思ったのは、やっぱり『おとなのためのピアノ教本』は少々難しいということです。
『おとなのためのピアノ教本』の大きな特徴は「調についてしっかり学習」ということですね。コードネームとともに。
一方『シニア・ピアノ教本』は、示された和音ををそのまま弾くという形。
各調とそれぞれの主要三和音を学び、コードネームも書かれていますが、「転回形」についての説明はなく、展開された和音をそのまま弾くようになっています。
また、『おとなのためのピアノ教本』のように、「コードネームのみを見て弾く」という課題はありません。
「弾く」ということに関しては、同じレベルまで進むことができると思います。
でも、『シニア・ピアノ教本』3巻を終えて『おとなのためのピアノ教本』の3巻に入るのはちょっと難しいかも。
いきなりオーグメント・コードからスタートし、分数コードも出てきます。ちょっと「??」状態になってしまうのでは・・
コードの部分でついて行けなくなってしまうのではないかと思います。
調についてきちんと学んでいきたいということなら、『シニア・ピアノ教本』3巻終了後、『おとなのためのピアノ教本』2巻へ入るといいかもしれません。
2巻は、ハ長調の音階からスタートです。両手で音階を弾くことから始まります。
『シニア・ピアノ教本』ですでに終えている内容もありますが、コードの穴埋めもあるので、きちんと確認しながら少しずつ進めるといいかと思います。
『おとなのためのピアノ教本』、『シニア・ピアノ教本』それぞれの特徴があります。
自分の力や目指すところなどと照らしあわせて、自分に合った方を選んでいけるといいですね。
(公開日:2018年2月8日 最終更新日:2024年3月22日)
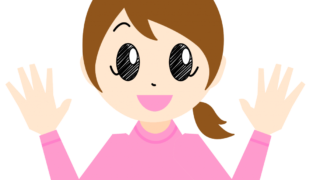



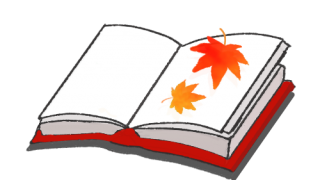




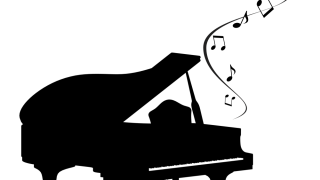








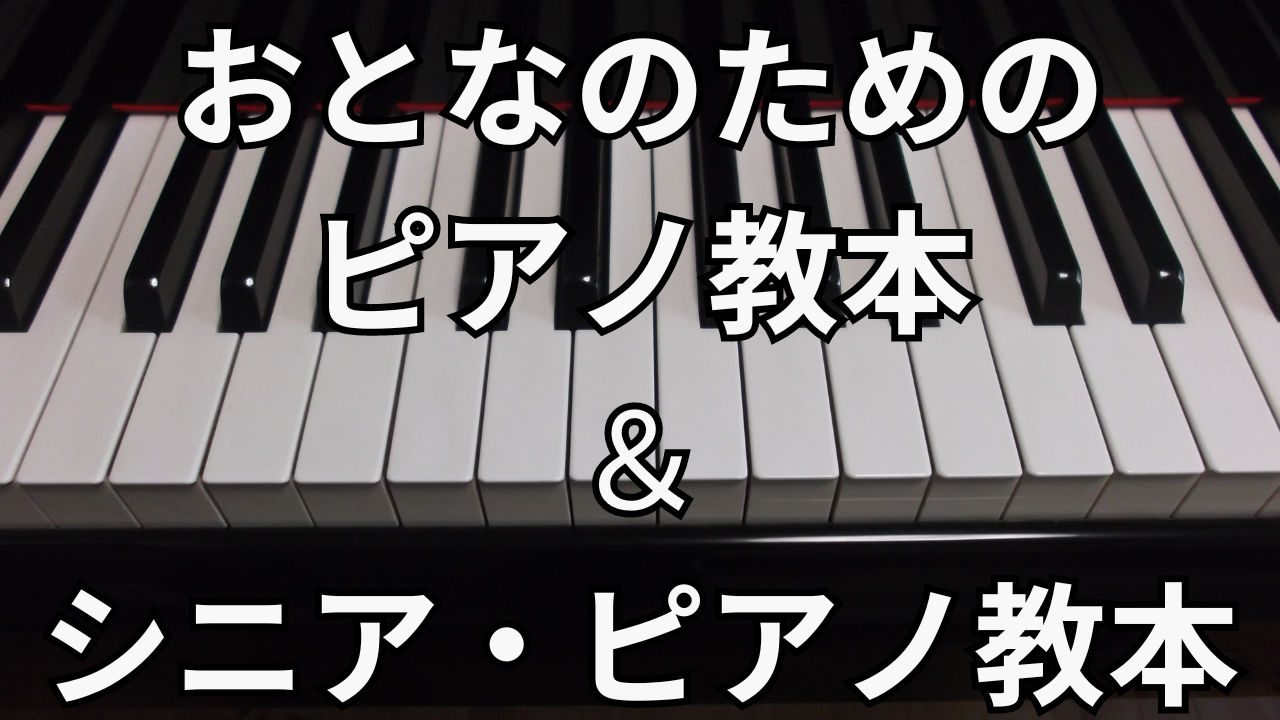












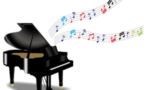
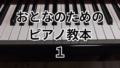

コメント