ピアノを弾くときに「指を速く動かす」ということはとても重要なことですね。
スラスラとスムーズに指を動かすことができると、演奏できる曲の幅も広がります。
速い曲をサラ~~っと弾いたりすると「すご~い」となったりするし。

それができるから良い演奏ってことでは全然ないんだけどね。
そして同時に、なかなか難しいことでもあります。
どうすれば指を速く動かせるのか、手の形、という視点からまとめてみます。
指を速く動かすために・・ピアノを弾くときの基本の手の形
まずは、ピアノを弾くときの手の形の基本についてまとめます。
ポイントは次の3つです。
- 鍵盤と手のひらを平行に
- 指は自然に丸く
- 関節はどこもへこまない
さあ、弾くぞ、と鍵盤に指をのせたその時の状態です。
こんな感じ⇩

まずはこの形をつくる。それから指を動かして弾き始めることになります。
以下に、一つ一つ詳しく書いていきます。
鍵盤と手のひらを平行に
鍵盤と手のひらは並行にします。
手首が下がりすぎても上がりすぎても、ピアノは弾きづらくなります。
そして、小指側にも、親指側にも傾かないようにします。
ありがちなのは、小指側に傾くこと。
腕をダランと下に下げたときに、手のひらは内側(斜め後ろ)を向きます。
それが自然な形です。
その自然な形のまま、手を手の甲を上げていくイメージで鍵盤の上に持っていくようにして手の準備をします。
その際、「脱力、脱力」と意識するほど、小指側へ傾いてしまいます。
これは、少し意識して小指側に傾かないようにする必要があるんです。
小指側に下がらないようにするには
小指側に下がらないようにするには、肘を少し外側へ出します。
あくまでも、肩関節を使って肘を動かします。
手首だけを動かして直すのはよくありません。
腕に少しツッパリを感じるはずで、不自然な形だということがわかると思います。
手の様々な動きは、腕の外側から小指にかけての線を軸にして行われます。
なので、ピアノを弾く際も、腕から小指にかけてはまっすぐになっていた方がよいです。
小指側に下がらないようにしつつ、腕から小指にかけてまっすぐになるように肘を動かします。
そして、肘を動かすときは、肩も意識する必要があります。肘は肩からつながっているのですから。
肩から動かす意識で肘を動かします。
参考文献→『ピアニストならだれでも知っておきたい「からだ」のこと』」よりP.94~P.100
紹介記事→参考文献『ピアニストならだれでも知っておきたい「からだ」のこと』を詳しく紹介しています。
指は自然に丸く
指は、自然に丸くします。
腕の力を抜いてダランと下に下げたとき、指は内側に丸まっていますよね。
その形のままでよいです。意識して丸める必要はありません。
関節はどこもへこまない
上に書いたように自然な状態のまま鍵盤に手を置けば、関節はどこもへこんでいないはずです。
指の関節も、手首も。
関節がへこまない状態は、ピアノへ効率よく力を伝える(鍵盤を最小限の力で押す)ためにとても大事なことです。
以上のような手の形を基本に、指を動かしてピアノを弾くことになります。
関連記事→ピアノを弾くときの基本的な手の形と指の動かし方をまとめています。
指を速く動かすための具体的な弾き方

それでは、指を速く動かすための弾き方をみていきます。
指を速く動かすために最も大事なことは、指には力を入れないということです。
指に力が入ってガチガチに固まっていては、指をスムーズに動かすことはできません。
最も大事で、最も基本的なことですね。
そして、
このことが、とても大切になります。
こんな感じ⇩
指だけが動いている、ということ分かるかなぁ‥。(う~ん、おばさんの手だ)
「手の形」をしっかりと保つ、とは?
「手の形」をしっかりと保つ、というのはどういうことか。
「しっかりと保つ」というのは、ぎゅっと力を込めることではなく、”支える”という言葉がしっくりくるかと思います。
つまり、
ということです。
次の音への移動を素早くスムーズに行うために、手首は柔らかくしておかなければなりません。
そして、指は自由に楽に動かせるように、ギュッと固めてしまわないようにします。
腕が下がりすぎても上がりすぎても弾きにくくなります。
自分に合ったちょうどよい位置で、ちょうどよい力を入れて支えなければいけませんね。
指を速く動かすために・・自分に合った「手の形」を見つける
基本的な手の形や、指を自由にするための”支え”までを確認できたら、あとは弾いていくことになります。
実際に速いパッセージを弾いてみて、音がきちんと出ているかを確認しなければいけません。
頼りない音になっていたり、滑ってしまっていたり・・そんなことはないでしょうか。
最終段階は、きちんと求める音が出せているかを見ていかなければいけません。
そのために、
この必要が出てきます。
「手の形」の微調整
いちばん上の章で、基本的な手の形について書きました。
鍵盤と手のひらを平行にする、とか、小指側に傾かないように、とか。
基本的にはそのようにする必要があると思いますが、「どの程度」というのは個人差があります。
そのために、微調整が必要になります。
手の大きさや指の長さなど、手の形は一人一人違っているからです。
その際のポイントは、
ということです。
ピアノは、鍵盤を下げる(押す)ことで音が出る楽器ですが、鍵盤へ効率よく力を伝えるためには、鍵盤を垂直に押さなければいけません。
指が、鍵盤へ向かって垂直に落ちなければいけないということです。
指は手の内側へ曲がるようになっています。それを鍵盤へは垂直に向かわせるわけですから、ピアノを弾く際の指の角度が重要になってくるのです。
指は今よりのばした方がいい、とか、手首は上げ気味(もしくは下げ気味)の方がよさそう、とか。
そういうことを、弾きながら調整していくわけです。
基本は親指低く小指高く
自分の手に合った弾き方になるよう、手の形を微調整していきますが、それにも基本があります。
それは、
ということです。
手を見れば一目瞭然ですが、親指は指の付き方が他の指とは違っています。しかも短い。
弾く際も、他の指は手のひら側に曲げることになりますが、親指は横へスライドするような動きをさせなければなりません。
そのため、少し手首を下げ気味にして鍵盤に近づけることで、鍵盤へまっすぐ向かえるようにするのです。
逆に他の指は、付き方も同じで親指よりも長い。そのため、親指よりは手首は上げ気味にします。
小指は、短いですしちょっと細くて弱そうに見えますが、1番外についているため可動域は広く結構力があります。
なので、親指のように手首を下げて鍵盤に近づける必要はありません。
あまり近づけすぎると小指側に傾いた形になってしまいますし、短いためまっすぐに鍵盤へ向かえなくなってしまいます。
手のひらは平ではなく弧を描いていますよね。小指側は自然にしていて少し下がっているはずです。その程度の下がり具合でちょうどよい、ということですね。
参考文献→『シャンドールピアノ教本』よりP.81~P.86
指を速く動かすために・・何度も弾いて研究を
指をスラスラとスムーズに動かすための弾き方を、手の形の視点からまとめてみました。
大事なのは、指は自由にさせておくこと。そのために腕でしっかり手を支えること。
そして、基本の形はありつつも、自分にあった弾き方を何度も弾いて見つけること。
だと思います。
速く弾くときの弾き方は、速く弾きながらしか見つけられません。
速い部分を弾きながらいろいろと研究をしてみてください。
(公開日:2018年5月23日 最終更新日:2023年2月21日)
参考文献紹介記事→こちらの記事で『ピアニストならだれでも知っておきたい「からだ」のこと』を詳しく紹介しています。
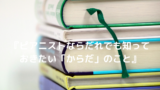
関連記事→ピアノを弾く時の基本の手の形と指の動かし方をまとめています。
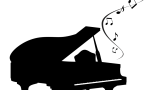
あわせてチェック→ピアノの練習に関する記事の一覧です。お好きな記事を選んでお読みください。

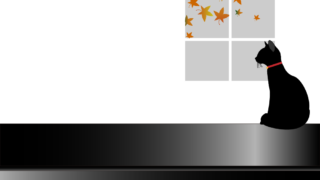
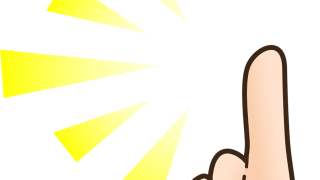


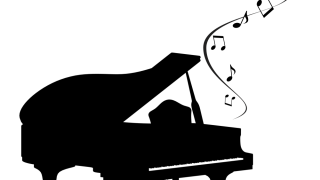


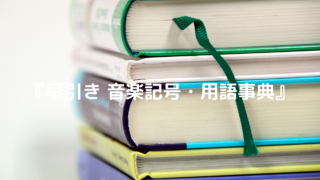



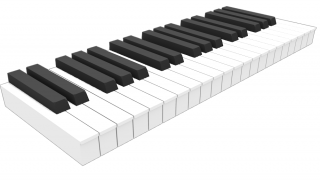


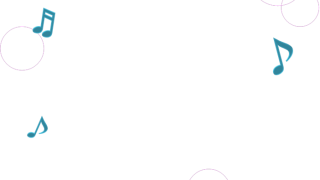

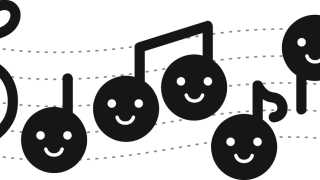
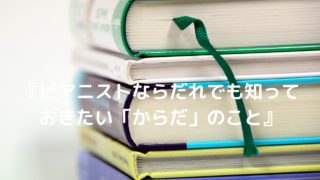
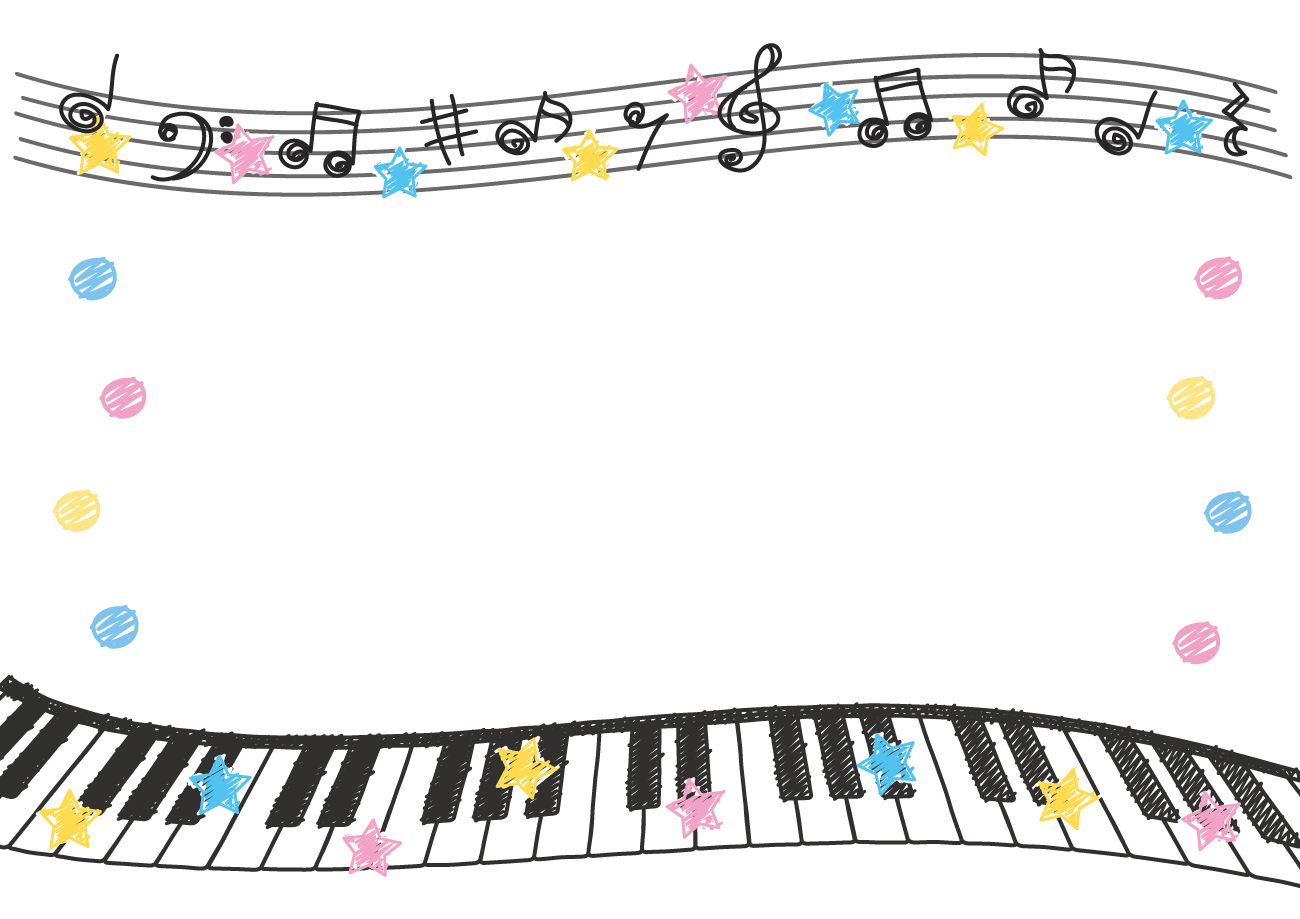




コメント